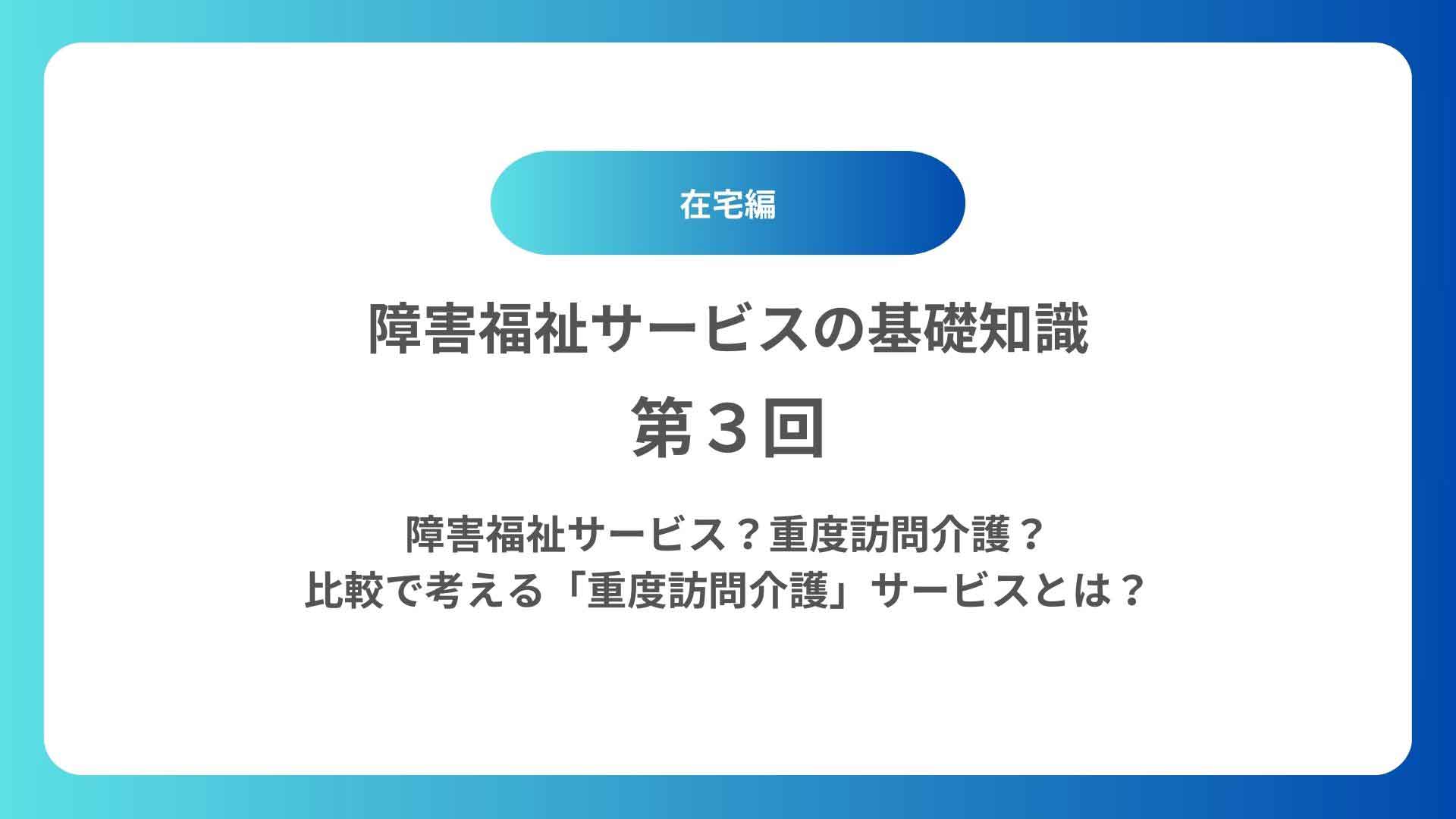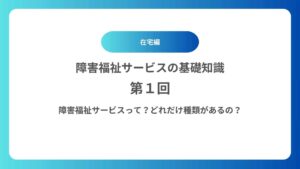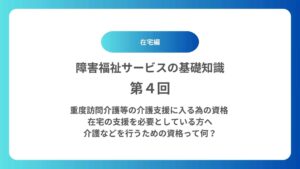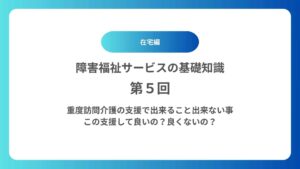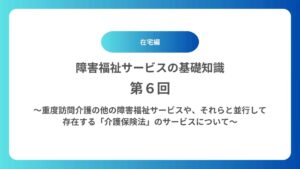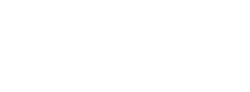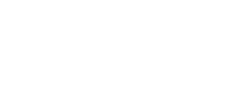重度訪問介護 障害者の歴史から垣間見える「重度訪問介護の本質」
はじめに(前回の振り返り)
前回は、障害福祉サービス制度の中における「居宅介護」と「重度訪問介護」の二つの制度を比較しながら、重度訪問介護制度におけるサービスについての基本を書かせていただきました。
二つを比較しながらの結論をまとめさせていただきました。次のように書かせていただいたはずです。
●「居宅介護」は、比較的短時間で事前のプランニング通りに支援する。支援内容についても「身体介助」「家事援助」「通院等介助」など、区別や種類がある。
それに対して
●「重度訪問介護」は、長時間の支援が大原則であり、身体的な支援のみならず家事援助や入浴や外出(場合によって通院等も含む)というように、それらを「見守り等とともに」「総合的に」支援する。
というようにです。
その他の違いとして、重度訪問介護の場合にだけ、とりわけ「コミュニケーション支援」という独特な支援や「入院中の支援」も行うことができる支援であるということなどを簡単にですが紹介させていただきました。
そういった前回までの話を踏まえて、今回は重度訪問介護制度の確立までの歴史を簡潔にではございますが振り返りつつ、「重度訪問介護制度の本質」について私の私見も織り交ぜながら様々な観点から書き綴っていこうと思います。
(Ⅰ)近現代以前(障害者運動以前)の時代
(1)有史以前
今現在においても「障害者」が存在するように、現代用語でいうところの「障害者」は有史以前から存在しているものと考えることが自然なものと考えます。
改めて言うまでもなく(今で言うところの)「障害者」と言っても様々な種別の障害者の方がおられるので、大昔の(今で言うところの)「障害者」の方がどのような種別の方を言うのかは、歴史学者や民俗学者の方が専門性が高く詳しいことと存じます。
ですがざっくりと、「(特に、他者に認識しやすいという意味で)体の不自由な方など」という意味合いで「障害者」を考えてみたり、多少様々な情報を調べてみると、興味深い事柄を知ることができます。
例えば、私の周囲(良心的な親族及び学校の先生や地域)の皆々様から聞いた事があった事は、良い意味でも芳しくない意味でも「障害者」はそれぞれの地域性や小さい集落の考え方で多種多様に捉えられていたと教えていただいた事であります。すなわち、
●障害者は弱く不完全な存在なので、今で言うところの「差別の対象」として存在していた。
●確かに障害者は弱く独力で、大変な当時の社会を生き抜くことは困難であることは改めて言うまでもなく、同様なことは健常者にも通じるものがあった。
そのような世情の中で「体の不自由な方が生まれた(今でいう障害者或いは障害児)」場合は、ごく少ない事例ではあるがその親族や当該地域において「地域や集落の人々が助け合って生きていくことを教示するための、神仏が使わした『神仏の化身のような存在』として、当該地域や集落の人々に認識されたりすることもあった。
というような話を聞いたりしたことがあります。
日本国内の話だけなのか。それよりももっと広い世界における話になるのか。そういった詳細も定かではありませんが、一言に「体の不自由な存在」というような障害者だとしても、様々な捉え方や考え方が存在した、ということ自体はあったようです。
(2)奈良時代後期もしくは平安時代以降
話を戻し日本の場合ですが、奈良時代後期もしくは平安時代あたりから、特に視覚障害者=盲人について、以下に書き綴るような考え方や制度が作られていったと言われております。
第54代の仁明天皇(在位833年3月22日~850年5月4日)の子供に、人康(さねやす)親王(831年生から872年薨去)がおられました。
人康親王は859年に病から両目を患って失明なされたと言われております。そのため出家して山科(現在京都市山科区)に隠遁したとのことです。
人康親王ご自身は、仁明天皇の第4皇子であり、第58代の光孝天皇の同母弟ということもあり、最終的な地位は「官位は四品・弾正尹。849年に上総太守に任ぜられ、852年に弾正尹に転任し、857年に常陸太守を兼ねた。」とされております。
その人康親王が失明なされた直後、出家して僧侶となられ、盲人を集め、琵琶や管絃、詩歌を教えたと言われております。
そのようなことから、人康親王が坐って琵琶を弾いたという琵琶石は、後に盲人達により琵琶法師の祖神として諸羽神社に祭られるに至りました。加えて「検校(けんぎょう)」もまた、剃髪し、正式な検校専用服(検校服 けんぎょうふく)は僧服に近く、また実際に僧職となる者もいた、と言われております。
ところで、「検校(けんぎょう)」とは、もともと平安時代や鎌倉時代に置かれた荘園と呼ばれる土地を監督する上級役職の一つであり、「勾当(こうとう)」は、平安や鎌倉時代の天皇のもとにある政府(=太政官)の中に存在した今で言う中級の事務職員のような役職をいいます。なお、勾当の上の上級職員(今て言う事務長のような)を「別当(べっとう)」といいます。
さて、盲人となった人康親王の死後、側に仕えていた盲人に検校と勾当の2官が与えられ、これが検校と呼ばれる「盲官(もうかん)=盲人のみが就くことができる役職」の始まりといわれております。
盲官とは人康親王の話に由縁するところから、仏門に入り、僧職となり、琵琶や管絃、詩歌を教える専門職として、盲人にいわば「専門職の地位」として朝廷(天皇のいる政府)から与えられるところとなっていきました。そのトップが「検校(けんぎょう)」というわけです。
(3)鎌倉時代~江戸時代(武家政治において)
鎌倉時代以降の武家政治が確立していき、いわゆる「幕府」による武家政権になるにつれ、琵琶だけでなく「平曲(へいきょく)(語り部のようなもの)」「三弦(さんげん)(三味線のようなもの)」「鍼灸(しんきゅう)(今の鍼灸師とほぼ同じ)」なども、専門職として盲人が行うようになっていきました。これらを行なう盲人は室町幕府以降において特に「当道座(とうどうざ)」という自治組織に所属することが推奨されていきました。
「当道(とうどう)」とは自らの芸道・集団を称し、「座(ざ)」とは盲人による琵琶、鍼灸、導引、箏曲、三弦などのそれぞれの団体を表すようになっていきました。そこから「座頭(ざとう)」という役職も発生しました。
最終的に、平安時代の朝廷、鎌倉幕府、室町幕府そして江戸幕府と時代が進みながら、「検校、別当、勾当、座頭」という序列で職位が定着していきました。
江戸時代は寺社奉行管轄下のもとで行われるようになっています。「芸事など」という対象と範囲は定まってしまいますが、専門職人として、盲人=視覚障害者については、古くから、様々な変遷を経ながらも「仕事を与えられるという意味で庇護」されていたと表現できます。
当然のことながら、これらの専門職を行いながら金貸しなどの金融を営んだり学者として活動したりなど、当人の才能に応じて活躍した事例もあるようです。
蛇足ですが、映画や時代劇で有名な『座頭市』ですが、その意味は「『座頭』という職位を任じられた『市という御名前の盲人』のドラマ」ということになります。
と同時に、映画での「座頭市」の中での「市(いち)さん」は、目が不自由でお仕事として「按摩(あんま)」をなされておりますが、あんなに剣術(特に抜刀術)に卓越していながら、それを教える=剣術指南(或いは武術指導)は、しないんですよね。ドラマ的には何となくもったいないです(笑)。
いずれにしても明治時代までは、多種多様な障害者はその時代その時代で存在していたわけですが、必ずしも「差別される対象」というだけではなくて「良い意味で崇められる対象」或いは「公的な存在」としても、その時代その時代を生き抜いていたという事実があるわけです。
(4)明治維新以降から第2次大戦後まで(盲官廃止令と新たな障害向け労働福祉政策へ)
しかしながら明治維新をきっかけとして、先述の「検校、別当、勾当、座頭」と呼ばれる専門職としての職位もなくなり、廃止されていきました。
明治4年(1871年)の盲官廃止令により当道座は廃止され、各地において芸能や鍼灸・按摩の同業者組合に再編成されていくことになっていきました。
鍼灸・按摩の同業者組合に再編成されていく中で「鍼灸師」或いは「按摩師」になるための国家試験受験資格を得るためには、今で言うところの「専門学校」や「(視覚障害中心の)特別支援学校」での職業教育課程が2年ないし3年間の養成課程として形づくられていきました。その際に、このような養成課程や養成機関を形づくっていく中で、
「晴眼者(盲人でない方=健常者)が入ることのできる養成機関を制限する」
というような政策を行うことによって、盲人の方への「労働福祉政策」として、当事者や関係者の運動によって、今で言う視覚障害者の方が経済的にも困窮しないようにと、明治政府以降で政策が進められていき、その歴史が今に至っているというのも事実であります。
その上で、時代は飛び越えでしまうのですが、現代において特に強調されている「規制緩和」や「障害者と健常者の分け隔てなく」という考え方に基づき、健常者の方への養成機関や専門学校への進学を開放することで、健常者の方への当該職業上の就職が広がりつつあります。
ですが逆に、健常者の方の按摩師や鍼灸師などへの職業の門戸を広げることで「障害者の社会参加=ノーマライゼーション)」を阻害してしまう可能性が発生してしまうのではないかと考える論者も存在し、極めて慎重な政策判断が今求められているところであります。
いずれにしても、何らかの形で、障害分野の一部分だけかもしれませんが職業的或いは労働的な福祉政策だとしても、多少なりとも日本において古くから存在しているということは心に刻んでも良いことであると存じ上げます。
とはいえ、先程「障害分野の一部分だけかも」と書かせていただきましたが、盲人であろうとなかろうと全員が資格者になれるわけでもないであろうことを推測すると、存在するであろう多くの多くの、大多数の「障害者」と評される方々については、そして「富国強兵」の名のもとに、多少なりとも心身などに不自由さがあるものは蔑まれていくようになっていったように考えられます。
「富国強兵」「帝国主義」などの明治時代から昭和初期(各種戦争を或いは、第1次世界大戦、第2次世界大戦)までは「戦争によって身体機能を失われた=『名誉の負傷』」を除いては、特に第2次世界大戦下においては様々な障害者が「非国民」などと評される場合があったという逸話を、様々な場面で、私事ではありますが筆者は一個人として耳目にしたことがあります。
(5)近現代(障害者運動)以前の時代の簡単なまとめ
これまで述べてきた通り、「検校」「別当」「匂当」「座頭」といった地位を獲得することが「盲人」は一部であったりしました。
ゆえに、別の観点から見れば、それ以外の障害者の大多数については、単なる「差別」という意味ではなく「生き抜くこと自体」について大変過酷なことであり、そしてそれは例えば「姥捨て山」という言葉にあるように、今で言う健常者と呼ばれる方に相当する高齢者で加齢による体の不自由さが出現して「生き抜くこと自体が大変な」という現実が転がっていたという当時の大きな時代的側面を、カッチリと日本の歴史上において、頭の中に踏まえておく必要があることは改めて言うまでもありません。
障害者の全体ではなくても「大昔から、労働福祉政策」的な、公のシステムが存在しつつも、他方で大多数の障害者が「命をつなぎ生き抜くこと自体が大変な現実」というのも存在している事実あるいは歴史というものを理解しておくことが肝要だと存じ上げます。
その上で、障害者にとってはとても厳しい時代であったと一個人として私こと感じる所以でございます。
(Ⅱ)障害者運動の黎明期
(1)第2次大戦直後の障害福祉制度の実情(障害者運動の開始のきっかけ)
1945年(昭和20年)のポツダム宣言の受諾により第2次世界大戦が完全に終了し、日本は戦時体制を終結することとなりました。終戦直後はいわゆるGHQの占領下にあり、当時の「大日本帝国憲法」の考え方から「自由」「平等」「人権」「平和」などを標榜する「日本国憲法」の制定に移行しつつ、社会のあり方が全ての社会側面において変化してゆく時代でありました。
そのような中、法律的には1946年(昭和21年)制定の旧生活保護法(新生活保護法は1950年=昭和25年制定)を皮切りに、1947年(昭和22年)に児童福祉法、1949年(昭和24年)に身体障害者福祉法、など、逐次その他の数多くの社会福祉に関わる法律が制定され、施行されていきました。
それらの制定・施行された多くの社会福祉に関する法令については、当該法律に基づき、通称「措置制度」と呼ばれる行政の命令に基づいて行われておりました。それは施設入所なども同じで、行政命令によるものでした。2003年(平成15年)の支援費制度が開始され、契約に基づく制度利用の開始までのことです。
そのような社会世情の中で、いわゆる「国立療養所」で生活していた結核患者でもある朝日茂さんは、生活保護法による生活扶助及び医療扶助を当時の金額で合計月額600円を受けながら生活をしておりました。
だが余りにも当時の金額としても低額すぎた事により、保護給付金の増額を求めて最終的に裁判に至りました。憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(=生存権)」と生活保護法について争った行政訴訟です。
昭和42年に最高裁大法廷判決がくだされましたが、この時すでに原告の朝日さんが亡くなられていたので「生活保護に関わる権利は相続対象ではない。」ということで終了の判決が下りましたが、この裁判の影響でその後の社会保障制度の発展に大きく寄与することになった最重要な事例となりました。
これがいわゆる「朝日訴訟」とよばれる重要な裁判例です。社会福祉を学ぶに当たっても、法律を学ぶに当たっても、必ず触れられるケースです。
そのような様々な裁判も含めて、徐々に社会福祉制度が進展しつつも、重度の障害者が施設或いは親元以外のところで、自らの意思で、生活を営むということは、制度的にはもちろん社会的にも極度に困難な高いハードルでありました。
(2)障害者自立生活運動の開始
1963年(昭和38年)に脳性マヒの当事者団体である「青い芝の会」が結成され、障害者の自立生活運動が始まりました。1968年(昭和43年)に「神奈川県青い芝の会」も結成され、同県内にて脳性まひ者を中心に自立生活運動が始まりました。
これらに触発され、脳性マヒのみならず「両手・両足・体幹等に重度の障害のある、筋ジストロフィー・頚椎損傷」などを原因とする全身性重度障害者が「常時介護(主に毎日24時間の介護)を必要である」と社会に対して声を上げるとともに、施設や親元を離れ地域で一人暮らしなどを行うにあたり、その生活に必要な常時介護を保障する制度を求める障害者運動が日本国内で行われるようになりました。
1970年代から、東京の府中療育センターの入所者が支援者(大学生などが中心)と共に入所中における介護の改善を訴え運動を行うに至り、都庁にテントを張り、そこで脳性マヒ者が2年間支援者の介助で暮らしたそうです。
この一連の運動の過程で、施設を出てアパートを借り、(時には大勢の)無報酬の支援者の介助で1人暮らしを始める脳性マヒ者が現れるに至りました。
当時、全身性重度障害者が在宅で受けられる公的介護制度は実質的にありませんでした。唯一存在するのは、
「高齢者対象の家庭奉仕員派遣事業について、1967年(昭和42年)に対象拡大して、所得税非課税世帯対象にのみ、身体障害者にも同じ制度を拡大及び創設した制度」
というものだけでした。名称も「身体障害者の家庭奉仕員派遣事業」というもので、親兄弟姉妹などで世帯対象として「所得税非課税世帯」でなければ対象とならない制度でした。
また、「(派遣される)家庭奉仕員」は今で言うところの「身体介助」のようなことはできなかったと聞きおよんでおります。そのようなことから、全身性重度障害者にとっては「在宅生活を支える公的介護制度は存在しない」ということに実質的になってしまうわけであります。
確かに、例えば「掃除や昼食の準備はできます」ですが、「昼食を飲食する介助や支援はできないし、トイレの介助についてもできません」ということであれば、全身性重度障害者は生活できませんもんね。少なくとも私自身は「生活できません」となります。
しかしながら、一つ一つの壁を乗り越えていきながら前述のような運動に続いて、一人暮らしをする全身性重度障害者が徐々に増えていきました。
駅や大学などで支援者募集のチラシを配るなど、障害者自身がその時の支援者とともに更なる支援者を募集するようになったわけです。そして、アパートなどで一人暮らしをする全身性重度障害者が増えていったというわけです。
(3)障害者自立生活運動の実情と実例
この当時の障害者自立生活運動の支援者というものは、完全なる無報酬の全くのボランティアでありました。障害者自身も、収入自体が生活保護などごくごく限られたわずかに存在する制度に頼ることしかできなかったからです。
2018年(平成30年)12月28日公開の映画「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話(監督:前田哲、主演:大泉洋)」が有名ですが、これは原作である、1959年(昭和34年)に北海道で生まれ小学6年の時に筋ジストロフィーと診断された鹿野靖明さんが1983年(昭和58年)に施設を出て自立生活を始めたときからの実話の書籍「『こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち』渡辺一史著作」をもとに映画化されているわけですが、この映画のようなことが実際になされていたというわけです。
なお、映画の主役の「鹿野さん」が自立生活を初めたのは1980年代に入ってからなので、障害者の自立生活を運動としてはかなり成熟期に入ってきている年代でありました。
全身性重度障害者の自立生活運動の開始が1970年頃からということを踏まえると、10年以上たっており、かなりの年月を経ていると言えると思われます。
(4)障害者自立生活運動の広がりには「多大な時間が必要」
ちょっとだけ話は変わりますが、福祉についての社会インフラの一つに「公共交通手段としての『介護タクシー』」が考えられると思います。
私が高校2年生の頃、つまり1991年(平成3年)に、京都や奈良方面に修学旅行に行きましたが、その当時「障害のある方の観光地の移動手段だとしても『リフト付きの介護タクシー』」というものが利用できる状態にあり、私自身も京都中心で利用させていただきました。私が在住している当時の山形においては、そのような介護タクシーは皆無の状態でした。
介護保険制度が日本で開始された2000年(平成12年)以降で、山形でもリフト付きなどで車椅子のまま乗車できる介護タクシーが現れてきました。私個人が初めて公共交通機関としての介護タクシーを利用したのは、2003年(平成15年)頃です。「介護タクシー」という視点からでも、その広がりは大都市と比較して10年以上の違いがあるようです。
脳性まひの当事者団体や神奈川県発祥の、障害者自立生活運動の開始(1960年代)から、先述の映画の「夜更けにバナナかよ」の実際の話の当時(1980年代)ということで考えると、全身性重度障害者の自立生活運動の広がりについて、日本全国に波及していくまで最低でも20年近くかかっているという証左にもなると考えられる所以です。
(Ⅲ)障害者運動の活発化と制度化の時期
(1)障害者自立生活運動の支援について「無報酬=完全ボランティア」の限界
話を全身性重度障害者の自立生活運動とその開始時代の1970年代頃に戻します。
全身性重度障害者が施設や親元を離れて地域で自立生活を行うような運動が徐々に活発化していきますが、それでもそれを支援する健常者=支援者は、依然として無報酬=ボランティアでありました。まさに「完全なる無償の奉仕」でありました。
そのような状況では、支援者になっていただける方は様々な観点から考えても完全な無報酬=ボランティアでも生活できる方に限られてしまいます。
例えて言えば、親御様などに生活を支えてもらっておられ、時間も一定程度の融通の利く学生の方などに必然的に限定されていきます。
しかしながら、そのような状況下では一例として学生の方で言えば、大学等を卒業すれば就職するわけで、学生ではなくなるわけで、「仕事と自分の生活」というものに時間を割くことになります。すなわち、ボランティアの支援者には継続的にはなれないということになっていくわけであります。
(2)障害者自立生活運動の支援の限界突破=運動や支援の「仕事化」
前述までのことから「無報酬での支援者の方への生活」という事実と向き合う必要が発生するわけです。
その解決方法の一つとして、支援者の方が「仕事として『介護という支援を行う。重度障害者等の方の生活を支える仕事行う』」というような支援者の生活を考えるという考え方が発生してきました。つまり、「(運動体としての)障害者自立生活支援運動」から「障害者自立生活事業体の形成」という考え方です。
全身性重度障害者の自立生活運動を考えるとき、「施設から出て地域で暮らし始める」などなど一定程度の目標は達成されたりする場合、「目標や活動が達成された」として評価されることになります。
しかしながら、仮に目標が「施設から出て地域で暮らす」ということであるならば、「施設から出る」という事が目標となるのか。それとも「地域で暮らす(暮らし続ける)」という事が目標となるのか。その辺のところも曖昧となりがちです。
後者の方を目標とした場合は「当該重度障害者が地域で暮らし続けて、いわば人生を全うする。天寿を全うする」という所までが目標の射程範囲となり得ます。その時の継続性のための組織づくり(事務局など)や責任体制などは、『運動体』のままでは曖昧になりがちであり明確性に欠くものでありました。
加えて、運動体の場合は目標や運動が仮に失敗に終わったとしても、誰も責任を問われず、運動体の社会的評価は下がる可能性が高いのですが、運動体を構成する個々人の生活自体については、素のままの生活状況が続くというだけで、それよりマイナスになるという可能性は低くなります。
そのような状況だと「自立生活運動」の『支援』を初めて行い続けたとしても、おのずと限界が生じてしまうこととなります。
要は、社会的責任を持ち得るような存在になる必要があるということとなります。日本国は、今で言うところの「修正資本主義社会」であるので、そのような日本社会の大原則を踏まえながら考えていかなければならないことになります。
その結果、「障害者自立生活運動体」は「事業体」としての性質も取り込みつつ、「自立生活センター」いわゆるCILという考え方を取り入れ、日本の福祉の歴史上初めて障害当事者を社会責任の担える主体者であると規定して組織体作りを行うに至っていきました。
つまりは、ボランティア活動等を中心とする運動体としては、行われることがどのような団体組織だったとしても無償奉仕活動であり、活動支援者の生活について考えるということが薄くなりがちという宿命を伴ってしまうということでありました。そこから脱却する必要があったということです。
(3)障害者自立生活運動⇒「自立生活センター CIL(Center for Independent Living)」
CILと呼ばれる考え方の組織だと「事業体」という考え方が強く入ってきます。ここでは、活動支援者は職員という形であり、彼らに給料が支払われるのは当然のことと考えられています。
「職員たる活動支援者に給料を支払って彼らの生活を守る」ことを団体の責任を負うものとして障害当事者が担いつつ支援を受けるという考え方は、支援を受ける側と支援を行う側での対等性を担保しようというような考え方になり「同じ人間」という考え方におのずとなっていきます。
と同時に、「支援を行うこと」は「支援というサービスを行うということ」という考え方に繋がり、「支援たるサービスの質を高める」という目標につながっていきます。事業体として組織作りがなされ運営されていくことを鑑みれば、事業についての運営計画や社会の中での様々な関わりについても学んでいく必要に駆られてゆくことになります。
それは、CILという組織体に関わる障害当事者や支援者について成長を促すものになるものと考えられます。と同時に、従前のような自立生活運動の活動も行うことになります。
すなわち「継続性」というものが大切なものとなり、そのような運営自体が「継続性の担保」に繋がっていきます。それらの結果、活動支援者の活動自体がいわゆる「仕事や業務」となり、活動支援者たる職員の生活が守られる、ということに繋がります。
そのようになっていくと、自立生活を行うところの地域との関わりについても取り組む必要になり、「仕事」という観点から、給与つまり賃金について考えてゆくことにもなり、その地域の福祉行政のあり方についても取り組んでいかなければならないことになります。
このような考え方に至っていくということは、障害当事者の社会的な立ち位置をもおのずと考えるきっかけにもなるので、大変重要な取り組みであったと思われます。
ここから「CILという団体」による障害者運動とともに並行して、地域行政や福祉行政との関わりや取り組み、つまりは障害福祉のあり方や或いは制度化について取り組む端緒となっていくわけでありました。
(4)CIL(自立生活センター)を通しての障害者自立生活運動と在宅介護支援の制度化
福祉行政や制度については、先述で掲げた通り日本国憲法(特に第25条)や生活保護法或いは身体障害者福祉法等の当時存在した各種福祉法分野に関わる法律に基づいて行われるものしかほぼありませんでした。
それらの制度は、施設に入所することを前提とするものがほとんどであり「施設や親元ではなく、地域で在宅生活を行う」ということを前提として制度化されたものではありませんでした。それらについても先に述べた通りです。
そのため、制度に関わる障害者運動としては、自立生活運動として、支援活動者=事業の職員となる方への給与の財源として「公的介護ヘルパー制度の補助金制度の確立」を目指すことになりました。生活保護法の中の様々な扶助(他に例えれば医療扶助など)の一環として介助に関わる扶助の成立も試みられました。
そのため、障害者運動が盛んである大都市(東京や大阪)の都庁や府庁、あるいは福祉制度の国の管轄担当である当時の厚生省(今の厚生労働省)への働きかけが活発化していきました。これらの働きかけの活動は、障害者についての社会の理解の浸透も含めて、交渉などの運動などが何度も行われていったようです。
その結果、ついに1973年(昭和48年)頃から国として行われる生活保護法に基づく生活保護の中に「他人介護料」と呼ばれる特別基準が創設され、厚生大臣の承認があればその「他人介護料」が生活保護を受けている重度障害者の場合、その制度を活用できるようになりました。それと前後して、東京都で全国に先駆けて「脳性マヒ者介護人派遣事業」というものが創設されていきました。
これらの制度は、障害者自立生活運動の中で、日本の中で、やっと産声を上げた制度でありました。
従って、厚生省や東京都などの行政の役割は財源を確保する=お金を出すということのみで、「実際の支援者或いは介助者の確保から育成教育、介助の運営などには行政はかかわらず、障害当事者もしくは障害者運動団体が自ら行う制度」でありました。そのような経緯から(障害者自ら自分の介助者を推薦するという意味で)
「自薦制度」と呼ばれることになりました。
ですが、無報酬=完全ボランティアであった支援者のあり方が、支援者の生活をも守られていくというとても大きな転換点であった事は間違いないものと思われます。
と同時に、真の意味で「CIL」の事業体としての考え方の部分が達成されていった瞬間であったと考えられます。ある意味、革命的な事柄であったとも表現できると言えます。
その後、生活保護における「他人介護料」については、国の制度であるところから地域的な意味で広がっていくまで時間がかかったとしても、他の制度と比べれば比較的すみやかな形で広がっていったようです。
しかしながら、東京都の「介護人派遣事業」の方については、東京都の事業費としても僅かなものであったため、介助者に支払う金額としては、交通費にも足りないような金額であったと聞いたことがあります。そこから、事業費の拡大と地域的な広がりを目標に、自立生活運動として様々な交渉が東京都や厚生省と当時行われていったということであります。
数少ないボランティアの方とともに交渉活動を継続する中で、病を得て亡くなる重度障害者もおられたようであります。しかしながら、そのような生命に関わる要望であり且つ交渉活動の努力の成果もあったのでしょう。「他人介護料」も「介護人派遣事業」の事業費も、対象地域も、徐々に広がっていくようになりました。
その結果、生活保護における「他人介護料」や東京都の「介護人派遣事業」の二つの制度は毎年改善され、どんどん自薦による制度の支給時間と支給される金額が伸びて行きました。 そして、1993年(平成5年)には東京都の全市区町村で、毎日12時間の公的な介護制度が受けられるようになるに至りました。
(Ⅳ)障害者自立支援運動の成果と介護保険制度開始に伴う障害支援制度の公的介護の抜本的な制度化
(1)日本初の「契約」に基づく公的な障害者支援制度=「支援費制度」
1997年(平成9年)制定及び2000年(平成12年)施行の介護保険法と、おおよそ時を同じくして、公的な障害者支援制度として「支援費制度」が2003年(平成15年)から始まりました。
高齢者や障害者等の違いを問わず、それまでの公的な支援制度は全て「行政措置」に基づく行政による命令で行われていました。
しかしながら、「介護保険法」も「支援費制度」も「事業者との契約に基づいて公的支援サービスを利用できる制度」として初めて導入されました。これらはとても画期的なことでありました(ただし障害児のみ施設入所中心に措置制度は残っています)。
高齢者の介護保険法及び介護保険制度については、このたびは割愛しますが、障害者支援においてこの「支援費制度」がようやく、「実質的に多くの障害者が公的な社会支援を制度として受けられるようになったもの」として受け止められ、実際にその利用者は、年々激増していきました。
「支援費制度」は介護保険法のような明確な「公的支援サービスのみを詳細に法的に制定された支援制度」ではありませんでした。
従前から存在していた身体障害者福祉法などを根拠にして、その対象者を公的に支援する制度として、介護保険制度を参考にしながら形づくられていた制度であります。
ですがこの時に、先述していた東京都内で発祥し東京都内の全市町村で拡充されていき、他の都道府県に広がりを見せていた「介護人派遣事業」が「(全身性重度障害者向け)日常生活支援」という形でホームヘルプサービスの一種として、「支援費制度」の中で制度化されました。
「支援費制度」自体が日本国全体向けに開始された制度であるところ、それまでボランティア等のように無償の支援などを中心として障害者の自立生活支援が行われていたことを踏まえると、名実ともに障害者の生活支援が「公的支援制度として、支援者が仕事として行うことができるようになった」瞬間でした。これはとても画期的な変革だと考えられます。
やはり「仕事として自らの生活を営みながら障害者支援を行うことができる」という事は、支援する側にとっても支援される側の障害者にとっても「変化という側面」一つだけで考えても多大な影響のある事柄だと考えられるからです。
他の視点から考えても「障害者自立生活運動」から発生した「ボランティアの方を中心とする支援による社会の自発的な障害支援」、続けて東京都から発祥の「介護人派遣事業」、そして「支援費制度による『日常生活支援』制度」という形に発展していった事は、まさに障害者活動家及び市民活動の結果が日本全国で通じる公的制度に成長したということを目に見える形で体現したからであります。
(2)「支援費制度の予算不足」と解決策としての「障害者自立支援法」の成立
さて、「支援費制度」は日本国内初めて在宅支援サービスとして「契約に基づく支援」としてスタートしたところ、その利用者は前述のように年々激増していきました。
他方で、サービスに特化された個別法に基づかない、いわば「厚生労働省内の一つの『(企画された)事業』」のような形で行われていましたので、各年度初めの予算額を超えるくらいのサービス利用が発生した時に「予算不足」などの問題を中心に、開始当初から様々な問題が発生しました。
難病の方や障害の種別によっては、利用できない障害者の方もおられるなど制度的にも未熟な部分が残されていました。
ちなみにこのような形での事業形態の場合は、例えば「予算不足」に陥ったとしても、政府内の一つの「厚生労働省の中の主催の事業の一つの予算がつきてゆく」ということに過ぎないので、「補正予算を組む対象の事業ではない」ということになってしまうのであります。
真逆の一例を挙げれば「生活保護という支援制度に特化した法律=生活保護法」に基づく制度の場合は「予算がなくなれば補正予算を国会に問うてでも当該法律=生活保護法を実行していかなければならない」ということが、行政府を担当する内閣及びその内閣の一つである厚生労働省の義務となるのであります。
このような「予算不足」問題を解決するために、2005年(平成17年)に障害者自立支援法が成立、2006年(平成18年)に施行されるに至りました。
この法律の制定によって「障害者を支援するということに特化した法律=障害者自立支援法」に基づき「当初の予算がなくなった場合、補正予算を国会に問うてでも当該法律=障害者自立支援法を実行しなければならない」ということになり、補正予算を組めるようになりました。結果「予算不足」問題は解決することになりました。
(3)障害者自立支援法の成立による様々な問題の発生と「重度訪問介護」制度の開始
この時に支援費制度の「全身性重度障害者への日常生活支援制度」というものが「重度訪問介護制度」というものに呼称も変化して、より充実した制度となったわけであります。
とはいえ、障害者自立支援法自体が制度設計の様々な討議の流れで介護保険のように「本人の1割負担」というものも導入されてしまい、ホームヘルプサービスのような在宅系支援だけでなく、就労支援系や施設入所系の支援制度についても「1割負担制度」が導入され
「応益負担(=サービスを受けるのは、受ける人にとって利益になるという考え方)」
に変更されたという新たな問題を抱える制度となってしまいました。以前の支援費制度の時は「応能負担(=サービスを受ける人の経済能力に応じて負担するという考え方)」という思考論です。
障害者自立支援法の制定と「応益負担」の導入の結果、先天性や中途障害を問わず「障害が重く支援を受けるサービスが多くなるほど自己負担も増えてゆく。だが、障害者の中心的な収入は障害年金のみであり過重な負担」でありました。
他に「就労支援などで作業所で作業を通じて働き工賃を得ても利用者としての自己負担の方が多くなり作業所などにも行けなくなってしまう」というような問題も発生してしまいました。
(4)「障害者自立支援法違憲訴訟」の集団提訴と、いわゆる「障害者総合支援法の制定」及びそれらの変化に伴う「重度訪問介護制度の充実」
2008年(平成20年)10月31日に、日本国内の八つの地方裁判所に「『障害者の自立』という法律の趣旨から反しており日本国憲法13条、14条、25条で保障される生存権の侵害」という主張のもとに「障害者自立支援法違憲訴訟」が集団訴訟として提訴されました。
その後、障害者自立支援法の運用の改善が試みられ「1割負担」という考え方だけではなく「経済力に合わせた、自己負担額の上限」という考え方の導入もあり、少しずつ変化していきました。
そのような流れとともに障害者自立支援法違憲訴訟の原告団・弁護団と国及び厚生労働省が2010年(平成22年)に裁判における「和解条項が裁判所で成立」することで和解し、集結するに至りました。その和解条項の中に「抜本的な解決」というものも存在したので、いわゆる障害者総合支援法が2012年(平成24年)に定まることになりました。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」=いわゆる障害者総合支援法が定められ、重度訪問介護制度も時の流れとともに運用改正がなされつつ現在も存在します。論客の観点によっては、現在の重度訪問介護でもまだまだ問題や課題が残されていると主張される場合が少なくありません。
しかしながら、私筆者は「障害福祉サービスの基礎知識 第2回目」の末尾の部分で次のように書かせていただきました。すなわち、
【「重度訪問介護」は、長時間の支援が大原則であり、身体的な支援のみならず家事援助や入浴や外出(場合によって通院等も含む)というように、それらを「見守り等とともに」「総合的に」支援する。】
というように…。
加えて、「コミュニケーション支援」や「入院中に支援」できることなどにも触れました。これらは、国または厚生労働省が中心に形づくられていった「介護保険法に基づく介護保険制度」には全く存在しない支援内容です。
筆者の「障害福祉サービスの基礎知識」の第1回や第2回における太字の部分のみでも良いので、「重度訪問介護」の部分を改めて読み直してみて下さい。
「重度訪問介護の中心は、『見守りとともに行われる支援』である。」ということが浮き出てくると思われます。
それはどのような手段や形式であったとしても、支援者と支援を受ける障害者が「『コミュニケート(=意思や感情を相手に伝えること)を行いながら支援を受ける」という根底部分が存在するからであります。
その源流は障害者の歴史を踏まえたものであり、それ以上に、戦後に発生した『障害者自立生活運動』を人生をかけて行ってきた先人の障害当事者と支援に当たった一般市民の皆様がたの成果に尽きると筆者は強く感じます。
つまり、現在運用されている重度訪問介護制度は「障害当事者と無償の支援を担当した一般市民の皆々様」によって形成されていった、
【「一般市民(=障害者や健常者などの違いを超えて、双方の立場の皆様)」によって培われた制度】
だという事実について深い理解を、今重度訪問介護制度に関わる皆々様は私自身も含めて肝に銘じておくべき事柄だと強く感じます。そしてそこに重度訪問介護の本質が形として現れているのが、何度も言うようですが、
【見守りとともに行われる支援】
という所にあるところも肝に銘じておくべきだと存じます。
その上で将来を見据えた時に、現在重度障害者の支援制度の中核として「重度訪問介護制度」は、その骨組みは確立されつつあると筆者は認識しております。
今後は『見守りとともに行う支援』という本質を、「重度障害者の人生の支援」ということを、公的介護制度=公的支援制度という観点を大前提に考えながら、重度訪問介護制度の更なる発展に今後関わる者の使命として自ら考えていく姿勢が大切になってくるのではないかと感じます。
つまり、感情論だけでは重度訪問介護制度の発展は制度論の部分が見込めませんし、制度論だけでは重度訪問介護制度の利用者=重度障害当事者のニーズ(=感情論)の部分の発展が見込めなくなるからです。
制度論の基本をきちんと踏まえつつ、あらゆる論点から重度訪問介護の発展を考える必要があるということだと存じます。
まとめ
「見守りをしていただきながら、時に雑談をしながら、天気が良いので外の空気に触れてみよう。」映画だと「夜中だけど、小腹がすいたから、バナナが食べたい、買ってきて!」普通に健常者であればできること。だからといって、支援してくださる方が困るようなことは避けたいというような私自身…。
お昼であるならば、買い物かねて散歩よし…。就寝2時間前のおやつ程度なら、自宅にあるもので、ちょっとプリンを食べてみる。
支援者の方とコミュニケートしながら、自分の人生を考えながら、より良い支援を目指したいものです。
「見守り」
簡単そうで最も難しいような支援だと私自身は感じます。そしてその延長線の上にある「総合的な支援」…。
重度訪問介護とは、支援者の方も、利用者の方も(特に私自身も含めて)そのような「成長し合えることのできる支援」という側面があり得ることを、改めて自覚しながら考えていくことができれば良いのかなぁと思います。
これからも、利用者の1人として重度訪問介護制度の本質と趣旨を考えながら、利用しながらその発展に関わることができたらと考える私自身が存在します。。。
今回はかなり長文になりました。最後まで読んでくださってありがとうございます。
また次回に!
当HP【土づくりレポート9月号】にて、齋藤直希さんをご紹介しております。

行政書士有資格者、社会福祉主事任用資格者
筆者プロフィール
1973年7月上山市生まれ。県立上山養護学校、県立ゆきわり養護学校を経て、肢体不自由者でありながら、県立山形中央高校に入学。同校卒業後、山形大学人文学部に進学し、法学を専攻し、在学中に行政書士の資格を取得。現在は、「一般社団法人 障害者・難病者自律支援研究会」代表。