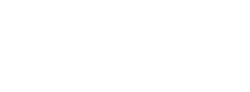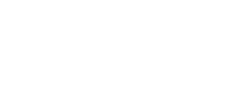手ごたえと実感【後編】
片岡亮太
26年前、撥(ばち)を通して感じた確かな手ごたえと、鼓膜を震わせた和太鼓の一音に自分の実存を実感できたことが、当時の僕には衝撃的な感動をもたらしたように、弱視、全盲を問わず、僕たち視覚障害者にとって、「実感を得る」ということが難しい瞬間は多々あります。
どれだけ歩き慣れた道であっても、普段と違うものが置かれていたり、工事や舗装、積雪などによって路面に変化が生じていたら、そこはまるで未知の世界。
大雨や強風が吹き荒れ、音の情報がかき消されてしまった時などは、白杖で足元を探る手に自然と緊張が走ります。
以前、探検家でノンフィクション作家の角幡唯介(かくはた ゆうすけ)さんが、闇に閉ざされた極夜の北極圏を旅した際の経験を書いた著書、「極夜行」の中で、一歩先の安全に確信が持てない状況で歩く不安について語っているのを読み、「これは我々視覚障害者の日常生活に近い!」と、思わぬところで共感したことがありました。
初めて訪れる場所はもちろん、慣れた場所であっても、目の前に危険が存在していないかどうか、実際に足を踏み出してみない限り確信は持てない。
もちろん白杖の使い方に熟達したり、経験を重ねることで、種々の察知能力は上がっていくし、バリアフリーやユニバーサル・デザインにより、相当量のリスクは回避できますが、突き詰めて考えると、視覚障害と共に生きることの実情とは100パーセントの安心とは程遠いと思います。
また、実害が生じることではありませんが、なじみの道と思っていた場所が、一瞬にしてその姿を変えることもあります。
学生時代、何年も通っていた、当時一人暮らしをしていたアパートから駅までの道を友人と歩いていると、「あそこに美味しそうな蕎麦屋があるね」と言われ、愕然としました。
毎日歩いている通りとは反対側にあったその店の存在を、僕は全く知らなかったからです。
現在のように種々の情報を、パソコンやスマホ、SNSを通じて簡単に取得できるようになる前は、同じようなことが頻繁にありました。
そんな時にはいつも、「そうだったんだ、今度行ってみようかな」と答えつつ、仕方がないことだとわかっていながらも、僕は本当にその道を知っていると言えるのか?この場所にいたと言えるのだろうか?
そんなことを考え、切ない痛みに胸を刺されていました。
だからこそ、誰かの誘導で道を歩く時、段差や道順など、不可欠な情報だけでなく、「あっ、桜が咲いてます」だとか、「もうすぐあそこにパン屋ができるらしい」など、目に入った情報を会話の中で伝えていただけたとき、まるで小学生の頃、白地図に様々な情報や色を加えていったように、僕の頭の中に広がる空間と地図にも、たくさんの彩が加えられる楽しさを味わうことができます。
近年、公私ともにパートナーであるジャズホルン奏者で作曲家の山村優子と共に各所に伺い、演奏をさせていただくようになったことで、公演の合間に観光に行く機会が増えました。
演奏会場自体が、由緒ある神社仏閣であることもあります。
ところが、主に日本において、名所や、世界遺産などとして知られている場所の多くは、僕にとって実感の伴わない場所になることが少なくありません。
そういった場所は、「触る」ことのできないものが多いからです。
歴史のある建造物が放つ独特の凛とした空気、匂い、周囲から聞こえる音を記憶にとどめることはできても、「どんな場所だった?」と後に聞かれたときに、明確に説明できる材料が乏しい。
その事実が、時に言葉にならないくらい寂しく思えることがあります。
そんな僕にとって、今でも忘れられない旅があります。
それは、2016年の4月、山村優子と二人で約2週間ほどバルセロナに滞在し、演奏やワークショップを行った時のこと。
スケジュールの隙間を縫って訪問した、サグラダファミリアや、やはりアントニオ・ガウディが設計したグエル公園など、観光地の多くには、視覚障害者へ配慮した、大きくて精巧なレプリカが配置されており、自由に触れられるようになっていました。
そこには、僕には理解できなかったものの、スペイン語の点字で書かれた解説文もありました。
さらに、きっと日本であればロープや柵が設置され、近づけないようになっているであろう石像などが、誰でも手で観察できるようになっていることも多い。
もちろん時にはロープなどでしきられている建物の柱などもあったのですが、優子さんに説明されている僕の様子を見ていた係員の方が、「この手袋を付けて直接さわってください」と、ロープの内側へ僕を連れて行き、実物に触れさせてくれるということも何度かあり、驚きました。
サグラダファミリアの有機的なフォルム、グエル公園に設置されたドラゴンの像の頭の丸み、ミュージアムに展示されていた、まるでテレビゲームのRPGを彷彿とさせるような中世の船のボディの形…。
6年近く経った今でも、確かな手触りと感動と共に、バルセロナ滞在の思い出は、僕の心に焼き付いています。
それは同行した優子さんにとっても同じで、彼女は実物を目にし、僕はレプリカを触りながら、
「この部分が○○色で日光を反射していてすごくきれいだよ」
そんな風に語っている瞬間、夫婦で同じものを楽しめている確証があり、旅の喜びを共有できているという確かな手ごたえがあったとよく話していました。
2020オリンピック・パラリンピックを契機に、様々な観光地やターミナル駅等のバリアフリー化が推進された近年。
僕たち視覚障害者にとっては点字ブロックが敷設されたり、音響式信号の量が増えるなど、「安全」の確保がしやすくなったことは本当にありがたいことです。
その一方で、それらの取り組みの延長として、旅行や観光の「実感」をもたらすため、触ることのできるレプリカの設置、視覚障害者へのガイドツアー、解説用アプリの開発や、例外的に実物に触れられる対応など、より確かな思い出を作ることのできる手段もまた、今後どんどん増えていってほしいと思っています。
日本を訪れた海外の視覚障害の方たちが、食事の味や、伝統音楽、空港に降り立った途端あちこちから香ってくるだしやしょうゆのにおいばかりを記憶にとどめるのではなく、スカイツリーや奈良の大仏、明治神宮や金のしゃちほこなど、直接触れて全体像を把握することが難しいものの形を知り、感動して帰国する。
そんなことが叶う日本になったら、国内に住む僕たちの生活もまた、より豊かで喜びに満ちたものになるのではないか。
オリンピック・パラリンピックの聖火がともした「多様性の灯」を、これからも絶やすことなく、僕たちの心にともし続け、それぞれにできる手段で、共生の道を切り開いていければと願います。
僕が伝える音や言葉も、その一助となりますように。
プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。