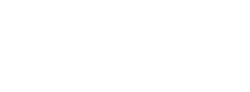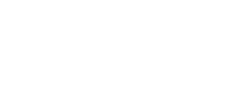「変わりゆく言葉」(後編)
片岡亮太
2011年に、ダスキン愛の輪基金の「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として単身渡米し、ニューヨークで暮らしていた時、障害を巡る新たな視点を得るために受講していたコロンビア大学内の教育学専攻大学院での「障害学」の授業では、主にインクルーシブ・エデュケーション(統合教育)を取り上げていました。
その中の一つの授業で使用した課題図書の冒頭には、「インクルーシブ・エデュケーションとは、障害のある子、障害のない子、ゲイやレズビアンなど様々なセクシャリティを持つ子、英語が第1言語の子、そうではない子、異なる宗教を有する子、白人、黒人など、多様な子供たちが共に学べる教育環境」と書かれていました。
インクルーシブ(包括的、包摂的)という言葉の対象となる範囲がこんなにも広いのかと衝撃を受けたことを、今でもよく覚えています。
当時の僕にとってインクルーシブ・エデュケーションや統合教育とは、障害のある子もない子も一緒に勉強できる学校やクラスの体制を指す言葉。
おそらくその頃の日本では、ほとんどの場合、そういった意味でしか使われていなかったのではないかと思います。
また同時期のアメリカでは、日本の福祉の世界でもよく使われる「自立」という概念について、「長年の間、英語では『Independence』という言葉が使われてきたけれど、『in』という接頭語には『一人で』とか『独力で』という意味合いが多分に含まれているのに対し、本来人として自然な生活というのは、他者を頼ったり、あるいは他者から頼られたりするなど、相互関係の中で自らの生活を確立していくことだという思いから、双方向のやり取りを意味する接頭語の『inter』を付与し、『Interdependence』という言葉を新たに作った」という話が盛んにされていました。
一つの言葉や概念に対する人々の考えが、時代によってアップデート(更新)されていくに従って、既存の言葉もまたどんどん変化させていくべき。
そんなアメリカ社会の視点に、しびれるものを感じました。
ここでは深く言及しませんが、以前、「バロメーターは同級生」の後編でも触れた、英語における「障害者」を意味する言葉の変遷にも似たものがあるように思います。
あれから十数年経った近年の動向はどうなのだろうかと気になって少し調べてみたところ、最近のアメリカでは、平等な社会に向かっていくための動きとして、「ディスアビリティ・ジャスティス」というムーブメントが起きているようです。
まだ詳しく理解できてはいないのですが、そのムーブメントにおいて、アートやダンスなどの分野で活動する障害のあるアーティストやパフォーマーたちによる、自らの障害に伴う経験や視点、社会への提言を表現の中に投影する取り組みが大きな推進力になっている様子。
「Justice」は公正とか公平を意味する言葉。
また、ここで言う「ディスアビリティ」は、心身の疾病のことだけでなく、セクシャリティやホームレス、一部認知症のことなどまで含まれていて、日本語で言うなら「社会的抑圧を受け得る人」が広範囲で含まれているようです。
「ディスアビリティ・ジャスティス」というフレーズ自体の響きもすごく格好いいし、そのムーブメントの中核をなしているのがアートやパフォーマンスの世界であることにも、一表現者として興奮を覚えずにはいられません。
しかも、こういった取り組み、僕はつい先日知ったばかりなのですが、どうやらアメリカではすでに10年近く続いており、アメリカのアート分野にしっかり根を張り、年々その社会的影響力を増してきている様子。
障害を取り巻く言葉、文化、社会的動き、それらがあたかも巨大な生物であるかのように、常にダイナミックに動いては変化し、成長している。
アメリカの状況を見聞きする度、僕はそんな思いに駆られます。
翻って日本はどうでしょう。
僕が失明を機に自分自身の視覚障害を意識し始めた10歳の頃から、もうすぐ30年が経ちますが、盲学校やろう学校、養護学校と呼ばれていた学校が、それぞれ視覚特別支援学校、聴覚特別支援学校、特別支援学校と法律や制度によって変わったり、バリアフリーやユニバーサルデザイン、インクルージョンやダイバーシティなど、海外からの影響でいくつかの言葉が広まったりはしたものの、そういった変化の中に、アメリカのそれのように、社会を巻き込むほどの大きなうねりのようなムーブメントや、そのきっかけとなる障害当事者たちの活動や運動は見えてこないように思います。
そもそも、「障害」という言葉自体、もう使われ始めて何十年も経ちますが、それに代わる新たな言葉や概念の登場には至っていません。
昨年読んだ『障害者差別を問いなおす』(荒井裕樹著)という本の中に、「言葉のアップデートがなされないことは、その問題の社会における関心の低さを示している」との記述がありドキッとしました。
確かに、「○○ハラスメント」という言葉で評される種々の嫌がらせや、言葉の暴力等の行為は、年々細分化され、その言葉が変化し、広がるスピードもかなり速いように思います。
また、LGBTをはじめとする性的マイノリティの方たちについても、英語圏のように、「She」や「He」に変わる、新たな代名詞を作り上げるというところまではいかないまでも、この10年くらいの間に、呼称のされ方や、メディアでの取り上げ方はずいぶん変わってきたし、社会的認知度も明らかに高まっているように思います。
いずれも、多くの人が関心を寄せ、現状に問題意識を抱き、より良い状況を生み出したいがために言葉を変化させ、知識を流布しているのだと思います。
けれど、障害について語る時、僕たちは未だに、「優生思想」や「自立」、「差別」、「偏見」など、おそらく昭和の頃から使っているであろう言葉ばかりを用いて議論し、思考することが少なくありません。
もちろん、使っている言葉が同じであっても、そのうえで、社会的な変化は無数に起き、欧米諸国に誇れるような取り組みや、日本ならではの素晴らしい活動も数えきれないほど存在していることは理解しています。
ただ、こと言葉に着目した時、昭和から元号が二回も変わったのに、日本における障害の分野は、その波に乗れていないと言わざるを得ないように思います。
アメリカでは最近、黒人の人たちが自分たちが培ってきた文化や歴史などに、プライドとアイデンティティを抱いていることを示すため、あえて自分たちのことを「ブラック」と呼んでいるように、障害者たちもまた、かつて侮蔑的でネガティブな意味で使われていた「クリップ」という言葉を、自分たちを称する際に使うようにもなっていると聞いています。
当事者によってもたらされる、こういった言葉の使用の変化はもちろん、ディスアビリティ・ジャスティスの潮流をリードする役割をアートの分野が果たしていることを考えるならば、今、日本で同種の変化が生じていない原因の一端は、全盲である演奏家の僕にもあるはずです。
2023年、既存の言葉や長年使われ続けている言葉だけでなく、新しい言葉、新しい表現、新しい価値観に向かっていく、そんな力に満ちた活動を、展開したい。
社会に対する思いを今まで同様、言葉で伝えるだけでなく、音楽家としての活動の中にも溶け込ませていくことはできないだろうか。
新たな年の始まりに際し、そのようなことを考えています。
未知の言葉、そしてそこに込められるアップデートされた価値観、皆さんも一緒に作り上げてみませんか?
プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。