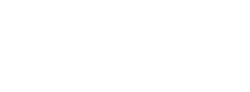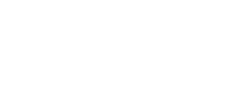「境界線を越えて」前編
片岡亮太
2011年、障害のある若者が海外で研鑽を積むことをサポートしている「ダスキン愛の輪基金」の第30期研修生として単身渡米し、1年間ニューヨーク市で暮らしていた時、僕は数多くの「小さなアシスト」と遭遇しました。
当時住んでいたアパートがあったのは、マンハッタンの北西部、「ウェスト・アッパー・ハーレム」と呼ばれる地域。
ご存じの方も多いかもしれませんが、マンハッタン島は東西に走る「ストリート」と呼ばれる道路と、南北を走る「アベニュー」と呼ばれる道路に区切られた碁盤の目状の地形をしています。
ストリートは南から順に数字が増えていくようになっており、アベニューには数字や人名、地名などがつけられているので、そのシステムや名前さえ理解していれば、現在位置や目的地のおよその位置の把握は簡単です。
僕は131ストリートとレノックス・アベニューが交差するところに手ごろなアパートを見つけ生活していたのですが、後になって知った情報によると、その頃、一般的には125ストリートより北部は、ハーレムの中でもやや治安の悪いエリアと認識されており、旅行客は足を踏み入れないほうが安心とされていました。
確かに、滞在中、何度か危険を感じたこともありましたが(これについてはまた別の機会にご紹介します)、僕にとってハーレム地区は、それ以上に「親切な町」でした。
数分も歩いていれば、通りかかった人が「誘導は必要?」と気軽に言ってくれたし、障害物にぶつかりそうになっていれば、「ゴミ箱があるからもう少し右を歩いたほうがいいよ」など、声がかかることが当たり前。
地下鉄の利用時、日本のようにホーム上に点字ブロックが敷設されていない駅が多いので、念のため白杖で端がどこかを確かめようとしていれば、文字通り四方から手が伸び、「それ以上行くと落ちるから、止まっていたほうがいい」と制止され、「乗りたい電車を教えてくれたら手伝うよ」と申し出てくれることも日常茶飯事でした。
おそらく彼らは、視界に僕が入った時点で、それとなく僕の安全を意識してくれていたのでしょう。
市内の別のエリアも度々一人で行動し、どこでも同じようなサポートを受けましたが、ハーレムほどの頻度で声をかけられたことはありません。
そのような場所で日々過ごす中で、ある時、横断歩道を渡ることに何の躊躇も抱いていない自分に気づいてびっくりしました。
それは、失明以後一度も抱いたことのない気持ちでした。
27年前、弱視から全盲になったことで最も怖くなったことの一つが「横断歩道を渡ること」。
信号が青になったら、まっすぐ反対側の歩道に向かって歩く。
たったそれだけのことに恐怖が付きまとうなんて、失明前には考えたこともありませんでした。
「弱視」、「全盲」と一言で言っても人それぞれに見え方は様々。
例えば、弱視という状態は視力の数値で、矯正視力0.01から0.3未満までと幅があるし、そこに、視野、両眼の差など、たくさんの要素が関係します。
全盲についても同様で、一切の光を感じない「盲」、光の明暗を認識できる「光覚弁(こうかくべん)」、目の前で振られる手の動きを認識できる「手動弁(しゅどうべん)」、目の前の手の指の本数を認識できる「指数弁(しすうべん)」という、4つの見え方に大別されます。
僕の場合で言うと、弱視時代は、右目がほぼ視野のない手動弁、左目は視野は十分あったものの視力が0.04から0.06程度。
色々なところで、不自由は感じていましたが、横断歩道の信号が見えなかった記憶はありません。
一方失明後は、右がほぼ盲、左もかろうじて光覚弁があるという状態。
信号の光はもちろん、目の前を走る車の動きを目で感知することも不可能です。
そのような場合、頼りになるのは音。
音響式の信号であればその音声、その他にも、車の走行音やエンジン音、周囲を歩く人の足音など、様々な情報を駆使して、信号の色の変化を認識し横断歩道を渡ります。
とはいえ、それも百発百中とはいかず、中学時代、自宅近くの時差式信号がある交差点で、まだ赤なのに青だと勘違いし、あやうく全速力のトラックに轢(ひ)かれそうになったことをはじめ、あわや大事故になっていたかもしれないという経験は枚挙にいとまがありません。
さらに、信号を正しく把握できていたとしても、まっすぐ歩かねば、無事に横断歩道を渡りきることはできません。
失明後、盲学校に転校し、白杖を使って独力で歩く訓練をしてもらっていた頃、道を渡ろうとしていたら、進行方向と並行して走る車の音に引き寄せられるように蛇行して歩いており、先生に止められていなければ、交差点のど真ん中へ出ていたということがありました。
視覚情報がない状態で、たった数メートル直進するだけのことがいかに難しいかは、実際に目をつむって歩いてみていただければ、おそらく皆さんにも実感していただけると思います。
そんな中、今日まで無事故で横断歩道を渡ることができているのは、数えきれないほどのヒヤッとする経験を積み重ねながら、目の前の安全を聞き取る観察力を養い、白杖や足の裏で、横断歩道の白線のわずかな凹凸を察知できるようになったり、身体の平衡感覚を磨けたことなどの結果です。
けれど、その実績は、決して安全を保証してくれるものではなく、車道に一歩踏み出す瞬間、「もしかしたら死ぬかも」という予感が、腰のあたりからせりあがってくるのを抑え込むのは容易ではありません。
ところが、ニューヨーク、とりわけハーレム地区で横断歩道を渡る時、僕はいつでも「大丈夫」という安心感を抱いていました。
「心配なら誰かに助けを求めればいい」そう信じることができていたからです。
実際、同じ方向に向かって歩いている人が、「自分もわたるから腕につかまりますか?」と聞いてくれることはしょっちゅうだったし、反対側から歩いてきた人が、「手伝いましょうか?」と言って、僕を連れてもといた方向へと戻ってくれることもよくありました。
だからこそ、車通りの激しい道を渡るときなど、音だけで信号の変化を認識するのでは不安だと感じたら、傍にいる人に、「一緒にわたってもらえますか?」と僕の方から声をかけることにも一切の躊躇がありませんでした。
もちろんここまでなら、日本でも人が多い都心を中心に街中などではあり得ることです。
特に近年は、気軽に声をかけてくださる方も増えたし、こちらから声をかけた時、すんなりと対応してくださることも多くなっています。
僕が在米中驚き、そして感動したのは、止まっている車さえも自分を助けてくれる存在になっていたことです。
信号が青になったことに確信が持てず、耳を澄まして前方の安全を確認していると、「青だから進んでいいよ」と僕の傍らで停車している車から声が聞こえたり、斜めに歩いていて危ない時には、「もう少し左、そうそう、もうちょっと、そのまままっすぐ」と、車内から声で誘導してもらったことも度々。
さらには、かなり交通量の多い道路を一人で渡ろうとしていた時に、すぐそばの車から女性がおりてきて、「一緒に渡ろう」と言って、僕を誘導してくれたことさえありました。
その時は、彼女が車に戻る前に信号が赤に変わってしまい、クラクションの大合唱になってしまったのですが(ちなみにニューヨークの人は、ちょっとしたことでもすぐにクラクションを鳴らします)、
「うるさいっ!視覚障害の人を案内しているんだから仕方がないでしょ!!」
という意味の言葉を、ニューヨーカー特有の悪口交じりで思い切り怒鳴った後、
「大丈夫大丈夫、気を付けてね、じゃあ!」
と、にこやかに言い置いて、その人は小走りで車へと戻っていきました。
嬉しくて、面白くて、温かい気持ちに心が満たされたあの日の一連の出来事を、きっと忘れることはないでしょう。
つづく
プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。