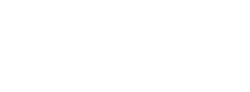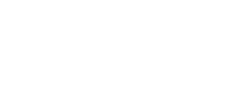「言葉と障害」~2
片岡亮太
僕が話したり書いたりする言葉の中には、どうしても風景や色、人の表情に関する情報が乏しくなりがちです。
一方で、音やにおい、手触りに関する表現は、無意識の内に磨かれているように思います。
視覚障害や聴覚障害があったり、車いすを使用していたり、あるいは、自閉症を代表とする、日本では軽度発達障害と呼ばれることの多い、「ニューロダイバージェント」に類していたりと、世間のマジョリティとは心身の機能の状態が異なっていた場合、その状況で暮らしている期間の長さに応じて、日ごろ発する言葉にも一定以上の特徴が現れるのは、おそらく自然なこと。
では、中途失明の僕が、「全盲の視覚障害者としての言葉」を身に着けるにあたって、何かきっかけはあったのだろうか?
そう考えた時、子供の頃のある出来事が思い出されました。
それは、まだ失明から日も浅く、小学5年生への進級のタイミングで、盲学校(現 視覚特別支援学校)に転校したばかりだった頃のこと。
担任の先生(晴眼)との会話の中で僕が、「そこの本を」のような言葉を口走った瞬間、「『そこ』じゃあ、全盲の人同士の会話だったら伝わらないでしょ。あなたも見えていないんだから、ちゃんとどこのことを言ったのかを言葉にしないと相手にしっかり理解されないかもしれないよ。」と指摘されました。
その言葉に強烈な衝撃を受けたことをよく覚えています。
弱視だったとはいえ、多少なりとも目が見えていた頃なら、「そこのそれ取って」で成り立っていたものを、「テーブルの左隅にあるペットボトルを取って」のように、場所と対象物を明確に言語化しなければ、これからは正確な意思の疎通ができないかもしれないのか…。
全盲になりたてだった僕は、そんなこと考えてもみませんでした。
確かに、いわゆる「こそあど言葉」と呼ばれる、「あれ」や「それ」、「あっち」、「こっち」などの指示代名詞とは、対象となっている物や方向を、会話の参加者全員が理解しているからこそ意味を成します。
でも、視覚情報を共有していない状況では、途端に何を指した言葉なのかがあいまいになってしまう。
例えば、コロナ禍をきっかけにしてYouTubeなどの動画サイトに多数公開された、プロのミュージシャンたちによる様々な楽器のレッスン動画。
僕も、舞台に立てない期間を、新たなスキルを会得するきっかけにしたくて、和太鼓以外の各種打楽器や趣味で弾いているアコースティックギターに関するものをたくさん視聴したのですが、大抵の場合、最も難しく、また大切なところに差し掛かった途端、「このようにやってください」とか、「こんな風にすると」という表現が多発します。
「それじゃあ僕には伝わらないんだ~」と、残念に思いながら、一つ一つの動作を丁寧に言語化してくれている別の動画がないかを捜すことが何度もありました。
そのくらい、「こそあど言葉」は、視覚情報があることを前提に使用されているもの。
だから、全盲の人同士の会話や、視覚特別支援学校の中での会話では無意識の内に「こそあど言葉」を避けるようになります。
「2時の方向に手を伸ばして」「そのまままっすぐ右に手を伸ばすと、腰の高さくらいのところにテーブルがあるので、その上に荷物を置いて待ってて」などなど、それはまるでラジオ中継のよう。
もちろん、だからと言って「視覚障害のある人には絶対に指示代名詞は使ってはいけない」と言っているわけではないし、それを使うことが失礼に当たるというわけでもありません。
事実、つい最近も我が家で、「あそこの柿の木がだいぶ伸びてきたよ」と妻が言った時、彼女は、その木の方向を見ながら話しているから、声の向きで僕にも通じるだろうと思ったようなのですが、自宅周辺には数本の柿の木があり、そのうちのどの木について話しているかの、確証が僕にはなかったので、「あそこってどこ?」と聞き返して、共通理解に至ったということがありました。
目が見えている妻と、全盲になって間もなく30年の僕との間で、とっさに出てくる言葉の選択において違いが生じるのは当然。
お互いの感覚をすり合わせながら毎日生活しています。
そして、僕はそのやり取りこそが面白いといつも感じています。
生まれつき、0.04程度しか視力がなく、今は光もほとんど感じない僕とは正反対に、両目とも1.5以上の視力を有する妻。
そんな彼女は、居間のソファーに座ったまま、数メートル先にある窓越しに庭の草花を見て、不意に「あっ、虫食いの穴が増えてる」と言ったり、かなり離れた位置に立っている僕が持っている薬のパッケージを目に止め、「あっ、それは胃薬じゃなくて漢方薬だよ!」などと言うことがよくあります。
弱視の頃、どれだけ目を近づけても新聞の文字さえ満足に見えなかった僕からすれば、妻の言葉は驚きの発言。
まるで超能力でも見せつけられたような心持で反応してしまうことが多々あります。
視力を持つ人が圧倒的大多数の環境にいると、「見える」ことが当然のこととして話が進むので、そこに、「そういう風に見えるんだ」などと口をはさむことは場の空気を壊してしまいそうで気が引ける。
でも、夫婦間の会話なら安心して聞くことができるため、僕はよく妻に、風景の説明を求めたり、「車を運転している時には、何をどのように目で追ってるの?」「どのくらい遠くから信号が見えているの?」など、「目で見える世界」について質問しており、それをいつも楽しんでいます。
なぜならそういう会話は、僕にとって「手に入らないもの」を知るチャンスだから。
介護福祉士や社会福祉士、ガイドヘルパーなどを目指す方たちに向けて講演をさせていただくと、「視覚情報の話題を会話に持ち出すのは失礼なのでしょうか?」と聞かれることが少なくありません。
相手が見えていないものについて語ることは、フェアじゃない、そういう発想から生まれる思いやりに基づいた質問なのでしょう。
確かに、そういった話題を好まない人もいると思います。
特に、視力を失ったばかりの人にとっては、自分には見えなくなってしまったものを突きつけられるようで、苦しく感じるかもしれません。
けれど僕は、言葉を通じて、美しい景色や色とりどりの植物、にぎやかな街並みの様子や、イルミネーションなど、僕の目には映すことのできないものたちに、少しだけ手が届いたような気持ちを味わえる、そういうやり取りが大好きです。
同様の意見を持っている視覚障害の人はたくさんいます。
このコラムもそうですが、僕たちが聴覚や触角を通して世界を認識しながら、日々生活している感覚を言葉にした時、多くの人が「面白い」と感じてくださるのと同じように、大抵の人にとっては当たり前である、目で見えるものについて知ることとは、視力のない者にとって、異文化に触れ、新しい視点を得ることと同意。
言葉によって、それぞれの感覚を知り合う作業とは、お互いの当たり前の視点を交流させる行為であり、それは間違いなく「多様性」を実感する手掛かりになり得ます。
だからこそ、障害の有無、障害種別、性別や世代を超えて、たくさんの言葉を交換し合うことが大切なのでしょう。
(続く)
◆プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。