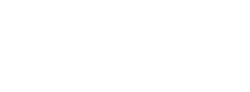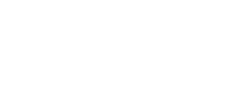「一人旅と車椅子」
片岡亮太
最近、ようやく舞台での活動が元の状態に戻り始めています。
コロナ禍によって日常生活が大きく変貌して早二年。
世界中の人がそうであったように、僕自身、それまでの当たり前の生活を手放さざるを得なくなった苦しさを何度となく味わいました。
中でもお客様を前にしての演奏や講演をはじめ、表現者としての中核を成す活動ができなくなったことへの悔しさは筆舌に尽くしがたいものがありました。
だからこそ、今、また多くの方々と、時間と空間を共有しながら、音や言葉を直接お伝えできるようになったことの喜びは大きく、毎ステージごとに幸せをかみしめては、心が震えています。
ですが、未だ手が届かずにいるものもたくさんあります。
その一つが「海外渡航」。
2011年に1年間単身ニューヨークで暮らして以後、僕は折に触れてアメリカを中心とする諸外国での演奏やワークショップのチャンスをいただいてきました。
本当ならば、2020年には、大使館を通じて現地の日本人会に3台の和太鼓を寄贈させていただいた中米のドミニカ共和国を訪問し、僕の講演や和太鼓の指導、公私ともにパートナーであるジャズホルン奏者で作曲家の山村優子との演奏などをさせていただくことが決まっていましたが、その企画は無期限延期のまま。
海外での活動は、まだまだ実施の目途が立ちません。
そういう歯がゆさを感じているからでしょうか、時折、唐突に在米していた頃のちょっとした出来事を思い出します。
2011年の6月、僕は「アメリカ障害学会(Society for Disabilities Studies)」のオープニングレセプションの中で和太鼓の演奏をさせていただくために、当時生活していたニューヨークから、学会が開かれるカリフォルニアのサンノゼ市に向かいました。
ニューヨークのジョン・F.ケネディ空港からサンフランシスコへは国内線で飛び、そこからはサンノゼ市のホテルまでシャトルバスを利用する。
日本国内であれば、飛行機の利用を旅程に含んだ移動を一人で行い、全国各地へ出かけていくことが当たり前だった僕ですが、英語に自信がないうえに、アメリカにおける公共交通機関での視覚障害者への対応について、まだ経験が浅かったあの頃は、トラブルを恐れるあまり、チケットやホテルの手配、移動の一つ一つの工程に至るまで、全てに緊張していたことをよく覚えています。
その出来事は、そんなドキドキの一人旅の中で起こりました。
ニューヨークのアパートからタクシーで空港に向かい、人に道を聞きながらチェックインカウンターにたどり着き、「搭乗までのガイドをしてほしい」と伝えると、間もなくして誘導のスタッフが登場。
これで無事に飛行機には乗れそうだと安心したのも束の間、なんとその女性は車椅子を携えていました。
アメリカの航空会社を視覚障害者が単独で利用する時、車椅子に乗せて誘導されることがあるという話は、以前から小耳にはさんでいました。
それだけでなく、「自分たちは歩けるのに、車椅子に乗せるのは不当な扱いだ!」と声をあげ、(詳細は忘れてしまいましたが)訴訟問題にまで発展させようとしていた人もいたという情報を得ており、僕自身もその考えに共感するところがあったので、ここは毅然とした態度で臨まねばと気持ちを引き締め、「僕は歩けるから車椅子は必要ないです。」とはっきり伝えました。
するとその人はとても軽やかな声で、「もちろん知っているわ。でも、こっちのほうが楽だと思うわよ。」と言ったかと思うと、あれよあれよという間に僕を車椅子に座らせ、小さな和太鼓や衣装、旅行中の着替えなどが入った大きな手荷物を車椅子の背中側のスペースに乗せて、颯爽と歩き始めました。
正直、あまり良い気分ではありませんでした。
自分がまるで、台車に乗せられた荷物にでもなってしまったような気がしたし、視覚障害者を誘導しながら一緒に歩くことが面倒だと思われているのだとしたら、それは差別的な対応ではないかとも思っていたからです。
けれど、ほどなくしてその女性は言いました。
「どう?これだと荷物の重さも関係ないし、私も誘導しやすい。それにあなたも座っていればよいだけだから気楽でしょ?」
そのにこやかな話しぶりを聞いているうち、かっかしていた頭が冷静になりました。
そう言われてみると、確かにすごく楽でした。
広い空港内を、重たい荷物を背負って、視覚障害者の誘導に慣れているのかもわからない、初めて出会うスタッフの人と歩くことと比べたら、座っているだけで、すれ違う人にぶつかる心配をすることもなく、搭乗ゲートまで案内してもらえることは、格段に安心だし安全。
しかもそのスタッフの人は、僕が歩けることは知ったうえで、快適な手段として車椅子を提案しているだけ。
そこには、僕に対する過剰な気遣いや、こちらの気持ちを無視してマニュアルに従っているような機械的な雰囲気はもちろんのこと、侮辱しているような様子も一切感じられませんでした。
「これはこれで合理的かもしれない。」
そう納得した僕は、完全に肩の力を抜いて、しばらくの間車椅子での移動を楽しみました。
実際、誘導されながら歩いている時以上に、周囲の音やにおいを楽しんでいられる余裕があったように思います。
そんなユニークな経験で幕を開けたサンノゼへの一人旅は、到着直後から渡米以後初となる風邪をこじらせ、数日の滞在中ずっとフーフー言いながら過ごすことになったことを含め、今でも忘れられない良い思い出です。
あれ以来、車椅子での誘導を経験した記憶はありません。
もしかしたらその方法に反感を持つ人が多くて、現在では廃止されているのかもしれないし、当時もごく限られたケースでのみ行われていたことだったのかもしれません。
けれど、今改めてあの時のことを振り返ってみると、そもそも僕は、なぜ車椅子に乗せられることを当たり前のように、「不当」とか「差別的」と考えていたのかが気になりました。
おそらくは、自力で歩けないと思われているのではないかということへの憤りや、視覚障害者に対する誤解を助長するという意識が主だったとは思いますが、正直なことを書いてしまうと、自分で歩きたいと主張する心の中には、車椅子に乗せられていることへの恥ずかしさや、その姿を周囲の人に見られたくないという気持ちがあったように感じます。
その思考は、気を付けていなければ、車椅子のことを否定的に考えたり、車いすユーザーの方たちを一方的に同情したり軽んじることにも繋がりかねません。
あの日誘導してくれたスタッフの女性のように、「こっちのほうがお互い楽でしょ?」という視点に立った時、僕たちの間で車椅子は、特別な意味を持たない、純粋に便利な道具として存在していました。
そこにネガティブな印象を付与していたのは僕の方。
他者から自分に向けられる態度や言動に対して、「怒り」や「恥」、「失礼」といった感情を湧きあがらせる時、その気持ちの根底には、コンプレックスや劣等感、そして、差別や偏見の影が隠れているのではないかと考えることがよくあります。
あの日感じた、車椅子の利用を拒む気持ちは、車椅子に乗っている姿は恥ずかしいという考えを、僕が無意識の内に抱いていたことの現れだったのかもしれません。
海外に出ると、日本とは異なる考え方や視点、文化や人々の言動にたくさん触れることで、当たり前になっていた認識が揺さぶられ、まるで瓶の底のほうに隠れていた沈殿物が浮かび上がるように、違和感や気づきという形で、心の中の小さな思考のかけらが可視化されることが多々あります。
一日も早く、また国境を越えて、そんな経験をたくさんできますように。
プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。