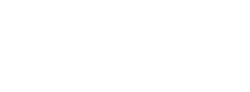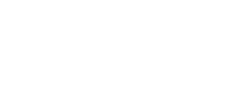「主役になれる場所」(前編)
片岡亮太
子供の頃に読んだ、黒柳徹子さんのご著書「窓際のトットちゃん」の中に、徹子さんが通っていた「トモエ学園」の運動会では(詳細は違っていたかもしれませんが)、極端に天井の低いトンネルを抜ける障害物競走を行い、低身長の児童だけがすいすい走って行けるようにするなど、障害をはじめとする身体的特徴のために、運動を得意としなかった子供たちが有利になるような競技を作り、彼らが目立てるチャンスを生み出していたことが描かれており、僕はそのシーンが大好きでした。
同校の校長先生の、一人一人が輝ける瞬間を作ろうとする発想に感動したからです。
思えば、僕にとっての盲学校(現 視覚特別支援学校)への転校とは、まさにそういう場所を得た感覚に近かったのかもしれません。
網膜剥離による突然の失明のため、弱視から全盲になった僕が、小学5年への進級時に、一般の小学校から地元の盲学校へ転校した当初、環境の激変に翻弄され、戸惑いながらも、漠然と感じていたのは、「主役になれる喜び」でした。
当時の母校のように、人数の少ない盲学校の中では、児童、生徒の誰もが何かしらの責任のある役割を持ち、様々な学校行事において、必ず一人一人に見せ場があることが当たり前。
転校初年度の学習発表会。
全部で10数名ほどの小学生全員で行った劇の中、僕に与えられた役割はナレーター。
点字の本を手に取り、それを読み進めるうちに、本の中で繰り広げられる物語が舞台上で演じられるという設定でした。
進行役ではあったものの、物語上の位置づけは主役。
しかも、失明から間もなかった僕にとって、舞台上を動く必要のない配役は、とても安心なもの。
実際には、まだ点字を読むスピードが遅く、形だけ点字をなぞるようにして、全てのセリフを暗記して臨んだのですが、たとえ演技だったとしても、「滑らかに本を読んでいる姿」とは、あの頃の僕にとってはもちろん、家族にとっても信じられない光景であり、マイクを通して大きな声で、堂々とストーリーテラーの役を務められたことが、自分自身信じられず、思わず泣けてしまいそうなほどに嬉しかったことをよく覚えています。
なぜなら、弱視の頃の僕には、そんな自分を、想像することすらできなかったからです。
転校前に通っていた公立の小学校は、今で言えば「統合教育」や「インクルーシブ教育」に類する環境でした。
通常の学級と、弱視の児童を支援するための「弱視教室」の両方に所属し、同級生と同じ教室で授業を受けることもあれば、弱視教室で担当の先生と一対一で、「拡大読書器」と呼ばれる、カメラが付属したテレビを使って、教科書やプリントを画面に拡大表示させながら授業を受けたり、図工の時間や校外学習など、みんなと行動する上で支援が必要なタイミングの時には、弱視教室の先生に来ていただいて、適宜アシストに入ってもらうなど、状況に応じた対応を受けつつ勉強する。
そのような対応ができる学校が、地元に隣接する市内にあったため、朝は同市内で働いていた父親の車で送ってもらい、帰りは母か、祖母に迎えに来てもらって通学していました。
そういう生活の中、幸いなことに、同級生が僕の障害を揶揄したりいじめたりすることはなく、むしろ当たり前のように手を貸してくれることがほとんどだったし、それと同じくらい当たり前にけんかをすることだってありました。
唯一記憶にあるのは、1年生の時、何人かの上級生が、僕を見る度「より目」と言っては、斜視をからかって笑われたこと。
ですが、それも一定期間続いた時に、いい加減しつこいと思い、かなりの剣幕で怒ったことで終息。
深刻ないじめ等に発展することはありませんでした。
だから、当時の僕の学校生活は、おおむね良好なものだったのでしょう。
ですが、そんな日々の中、僕がクラスの中で「一目置かれる」瞬間はほとんどありませんでした。
学年が進むにつれ、徐々に視力が下がり、一方で教科書の文字は細かく、複雑になっていく。
そのため、拡大読書器を使ったり、教科書自体を拡大コピーしてもらっても、一文字ずつゆっくり読むことしかできず、理解や読解に至ることが難しい。
そんな僕にとって小学生の宿題の定番、「本読み」や「漢字書き取りプリント」とは、拷問に近いもの。
本来なら、30分もあれば終わるような簡単な宿題に何時間もかけ、たどたどしく音読したり、光の強い読書スタンドをつけ、顔をプリントにぴったりくっつけながら、見えづらいプリントの枠の中に、漢字を書き入れた毎日。
(…、今、久しぶりにあの頃の宿題のことを思い出したら、当時、いつも味わっていた、情けないようなみじめさが戻ってきて、サーっと全身の血が引いていくような感覚や、胃の痛みを感じました。)
そんな状態でしたから、順当に学習できるわけもなく、成績はおそらくクラスで最下位だったのではないかと思います。
また、運動もからっきしだめだったし、周囲が何をしているのかを把握することも困難だったために、体育の時間の運動や、運動会などでの群舞なども、いつも頓珍漢な動きをしては、おどおど。
さらに、机から文房具やノートを落としても気づけないことが多かったため、「片岡君の○○が落ちてまーす!」と誰かに指摘されることがしょっちゅう。
おそらく当時のクラスメイト達にとっての僕とは、「お世話してあげる相手」だったと思うし、ごく普通の友人関係の中でも、「お味噌」とか、「豆っこ」と呼ばれるような、対等とは少し違って、みんなで守ってあげなければいけない存在、そんな風に思われていたのではないかと思います。
事実がどうだったかはともかくとして、僕はそのように感じていたし、そのくらいに僕の中には周囲へのコンプレックスがありました。
日本でJリーグが開幕したばかりだったあの頃、サッカーに明け暮れる友達が多い中、ろくにルールもわからず、また誰がボールをキープしているのかもよく見えていないのに、ただただみんなを追いかけて走って、格好良くシュートを決める友達にあこがれを抱いたり、いつでもクラスの輪の中心にいる人たちを見ては、自分が同じように目立っている姿を空想する。
それが弱視の頃の僕でした。
もしも、あのままの環境で暮らしていた場合、僕にナレーターの役割が与えられることなんて、決してなかっただろうし、僕自身も自分にそんなことができるだなんて考えもしなかったでしょう。
だからこそ、失明という、天変地異のような出来事を経て、期せずして知ることのできた、「主役になれる喜び」は、胸を熱くするものだったし、当時の僕の自分に対するイメージを180度転換するきっかけにもなりました。
プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。
Blog: http://ameblo.jp/funky-ryota-groove/
youtube: https://www.youtube.com/user/Ajarria