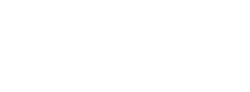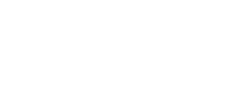津久井やまゆり園の事件から6年目に寄せる『自覚者の詩』
わたしの
ちょっと前に、非常に影響力のあるユーチューバーが「自分にとって必要のない命は軽い」「ホームレスの命はどうでもいい」という発言をして話題になった。
そんな出鱈目な。
無責任すぎやしないかい?
発言が正しいとか正しくないとか、そんなことを議論している場合じゃない。
将来就きたい仕事のベストテンにも入る、子どもたちに人気のあるユーチューバーという仕事をしているその一人が、
「社会に役立たない無用な者は、生きている価値がない」
なんて言ってしまったら、子どもたちが鵜呑みにして信じてしまうじゃないかよ!
有用な者しか生きる価値がないと思って生きることは、それから先の人生を生きにくい窮屈なものにしてしまう。
だって、有用な者にならねばと思って生きるのは辛いし、もし自分が何もできなくなったら捨てられてしまうのではないかという恐怖に怯えなきゃならなくなる。
その価値観はいずれ自分の首を絞めていく。
私がそうであるように。
◇
私は「能力が高い者こそ価値がある」ことを学校教育の中で教えられてきた。
今思えば本当はそんなこと全然大事なことではなかったし、本当に本当にもっと大事なことがたくさんあったのに、一つの価値観しかないような錯覚から抜けられず過ごしてきてしまった。
真面目に信じてきてしまった自分が悪い。
おかげで、いつの間にか自分自身の背骨には人を能力で選り分けようとする「ものさし」が存在することとなった。
その「ものさし」で私は他人をはかり、そして自分をはかり、窮屈に生きてきた。
それは当たり前すぎて、はじめは気づかなかった。
サングラスをかけていることを忘れて世の中の暗さを憂いている人のように。
その「ものさし」は、すっかり自分の体の一部に同化してしまっていたのである。
自分の「ものさし」の存在に気づいたのは、2016年に起きた津久井やまゆり園の事件がきっかけだった。
「意思疎通ができない者は生きる価値がない」
「生産能力のない者を支える余裕はこの国にはない」
そのような犯人の言葉を否定しようとすればするほど、私の背骨がうずいた。
人を能力ではかろうとする「ものさし」が、ここに確かに存在していることを主張してきた。
犯人と同じような価値観、いわゆる「優生思想」や「差別」が自分自身の中にある(「わたしの」中にある)ことをまざまざと突き付けられたのであった。
その日から、私は自覚者となった。
◇
………6年。
私には書けることと書けないことがある。
言えることと言えないことがある。
書きたくないこと。言いたくないこと。
おぞましすぎて、口に出すのもはばかられること。
はじめて書く。
少しだけ、書けるかな………。
私は、事件当日のあの夜のことについては一切触れていない。
それは考えることが辛くて、直視できないから。
その場にいた者以外は、誰だってその現場を知らない。それは当然だ。
だから直視なんて最初からできようはずもない。
私にできることは想像力を働かせることだけなのだが、例えば事件のあった日、7月26日、夏の盛の夜、むせ返るような熱帯夜、きっと虫の音が重なり合い、あたりに地鳴りのようにどよもしていただろう。
暗い廊下を非常灯の明かりが照らしていた。
………その場面に思いを馳せようとすると、私の想像力は強制的にシャットダウンしようとする。
見たくない。考えたくない。
やまゆり園の事件だけではない。
テレビで無惨なニュースがはじまると私はチャンネルをかえてしまう。見たくない。耳を塞ぎたくなる。
例えば、無抵抗な者になされる恐ろしい暴力。
ベランダから落下する高齢者、あらゆる身体拘束、ある幼児は浮き輪をつけられてお風呂に浮かべさせられていたという。
いじめにあい、真冬の公園の遊具のもとで凍死しなければならなかった命。餓死。
また、戦争だとは知らずに戦場に送られ、その場で知らされた兵士たち。
原民喜の『夏の花』に刻まれた原爆投下後の川辺に集まる人々の群れ。
………際限がない。
私の想像力はその場面の細部を再現しようとし、五感を研ぎ澄まし、今まさにここで起こっているかのように、時には自身がそれを受けているかのようなリアリティに襲われる。
どんな気持ち?無垢なまなこが見ていた世界。最後に見ていた世界はどんなものだっただろうか。
その場面の音。匂い。肌感覚。そのリアリティに胸がつぶれる。
おぞましくて、もう何も見たくない。考えたくない。シャットアウト。
他者のことが少しだけようやくわかってきたからこそ、苦しい。
自分のこととして考えられるようになってきたからこそ、拒否したい。
一方で、私は意気揚々と発言している。偉そうにどうのこうの言いながら、本当は目をつむり、耳を塞いでいる。
怖くて怖くてたまらなくて、顔を背けている。逃げようとしている。
そのくせどうにかしようとしている。
どうにかしなければと思っている。
顔を背けながら、進むべき方向を恐る恐る手さぐりしているような状態だ。
情けない自覚者である。