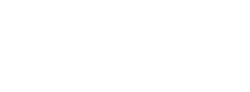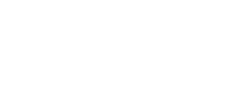「白杖とプライド」(前編)
片岡亮太
全盲の視覚障害者としての僕の日常は、たくさんのアイテムによって支えられています。
例えば、このコラムの執筆に欠かせないパソコンや、SNSやネットサーフィンの際に主に使用し、視覚障害者用に開発された支援アプリも多数リリースされているスマホ、点字でメモし、それを実際に触れられる点として表示することのできる点字ユーザーにとってのタブレットのような存在である、「点字ディスプレイ」と呼ばれる機器など、最近は、デジタルデバイスが大活躍してくれています。
一方、昔ながらのアナログなアイテムも、まだまだ現役。
コンサートや講演の際、時間の把握をするために使っている、蓋を開け、凹凸のある文字盤と、長針、短針に直接触れて時間を読み取る触察時計は、舞台中、太鼓の台にひっかけておくことで、音を立てることなく、まさにワンタッチでこっそり時刻をチェックできるので、今でも愛用しています。
さらに、地元三島市の広報や、市役所から届く一部の書類のように、紙に打たれた点字も、毎日点字の教科書や資料を読んでいた子供の頃と比べたら使用頻度は減ったものの、やはり大切。
そして、もう一つ忘れてはならないものが白杖(はくじょう)です。
失明後、初めて手にした小学5年の時以後、ほぼ全ての外出時、僕の片手には白杖が握られています。
仕事柄、日々の生活リズムを一定化することができないため、盲導犬の使用が適さないと思っている僕にとって白杖とは生活必需品。
自分のおよそ一歩半ほど先の地面を、肩幅より少し広いくらいの範囲で探り、目の前の障害物や段差を察知したり、時には軽く地面をたたき、その音の反響の仕方の変化を聞き取ることで、周囲の空間の広さや壁の有無などを知る助けとなっている白杖。
近年SNS等でも拡散されていますが、全盲の人だけでなく、多くの弱視の人も携帯しており、そのような時には安全の確保と同時に、自分が視覚障害者であることを、周りの人に伝えるための役割も果たしています。
都内で一人暮らしをし、電車移動を含め片道1時間程度をかけて通学していた大学時代や、マンハッタンのシンプルな道の構造と、あちこちを巡回していたバスや地下鉄のおかげで、一人で歩いて出かけることが容易だったニューヨーク在住時には、白杖を使っているからこそ、自由に、そして安全に外出できる喜びを味わっていました。
あの頃ほど日常的に長距離を歩いてはいませんが、今でも同じように思うことは少なくありません。
これまで、急いで走ってきた人や、すれ違う自転車に踏まれ、折れてしまったことも何度かありましたが、それはある意味で、「僕の身代わりになってくれた」とも言えるし、駅のホームを中心に、白杖のおかげで、文字通り命拾いしたと感じることもよくあるので、歴代の相棒たちには頭の下がる思いです。
生活に欠くことのできないアイテムであると同時に、社会的には、視覚障害者のシンボルのような意味も持つ白杖。
ところがそんな白杖を、僕は「恥ずかしい」と思っていた時期がありました。
それは、思春期だった中・高時代。
おそらく理由は、白杖を持っていることによって、「私は視覚障害者です」と公言しているようだったことと、それによって周りからの好奇の視線を集めてしまうことが嫌だったから。
今でも白杖を持つ僕を見かけた子供たちが、「あっ、目の見えない人だっ!!」と好奇心いっぱいの声を上げることがよくあるし(その声には、「授業で勉強した!」という嬉しそうな響きが感じられて、今の僕にとってはほほえましいものです)、まだそれほど体が大きくなかった頃には、白杖を使って歩く僕の周りに、同世代の子供たちが集まり、笑われたり、からかわれたりしたこともあったので、二十数年前の僕の自意識が取り立てて過剰だったのではなく、事実としてそういう側面はあったのでしょう。
そのため、当時の僕は、電車などに乗ると、たとえ立っていて、白杖がさほど邪魔にならないシチュエーションだったとしても、すぐに白杖を折りたたみ、バッグの中にしまっていました。
また、寮生活をしていた高校時代には、近くのコンビニまで白杖を持たずに出かけ、点字ブロックや歩道の凹凸などを足探りしながら、方向感覚と音の情報、そして記憶を頼りに歩き、勘に任せて買い物をすることで、同じく全盲の友人たちと、「度胸試し」などと言いながら盛り上がっていたこともあります。
当然歩くスピードが落ちるので、効率的ではないと気づき、あっという間に止めたこの行為は、純粋に危険なだけでなく、視覚障害者が白杖や盲導犬を使用して歩行することが道路交通法でも義務として規定されていることから、決して行うべきことではなかったと、今では反省しています。
けれどあの頃の僕たちにとって、「見えているように振る舞う」ことは、「格好いい」と同義でした。
もっと言ってしまえば、白杖を持つことをはじめ、視覚障害者然として振る舞うことは、野暮ったくて「ださい」とさえ感じていました。
だから、一人の時には携帯していても、弱視の友人と出かけるときには、「持つのが面倒くさい」などと言っては、わざと白杖を持たずに歩くこともありました。
それどころか、知らない形のものや草花など、手で触らなければわからないはずなのに、言葉だけ聞いて「わかった」ふりをしたり、道に迷っていたり、わからないこと、できないことがあった時にも、助けてもらったら「負け」のような気がして、何も困っていないかのように振る舞っていたこともあったほど。
その後の大学への進学や、学内唯一の全盲の視覚障害者であるという状況下で送った学生生活の中で、盲学校で暮らしていた頃とは違い、移動や学業をスムーズに行うためには白杖を使うことが必須になったり、手伝ってもらわなければ成り立たないシーンも多くなったことで、いつのまにか白杖に対するコンプレックスは消え、手助けを頼むこと、視覚障害のない友人たちの中、自分だけが様々なものを触って観察することにも躊躇がなくなっていきました。
また、学生時代、種々の不自由を認識し、それに対する支援を依頼することが、障害のある自分の権利を守ることであると気づいたことや、演奏家となって舞台に立ちつつ、社会福祉士として、社会の中にある不公平や不平等な環境を解消したいと願って活動していくうち、いつしか、視覚障害の象徴である白杖を堂々と握る手には、自信や「プライド」が宿るようになった気がしています。
弱視で生まれ、10歳で失明して以来、「もともとは見えていたはずなのに」。
そんな思いを心の片隅にいつも抱きながら生きていた10代の頃の僕にとって、白杖を巡る様々な葛藤とは、視覚障害を受け止めきれない自分との葛藤を意味していたように思います。
今振り返れば、そういう日々もまた、きっと、全盲である自分の身体を認めたうえで前進するために必要なステップだったのかもしれません。
プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。