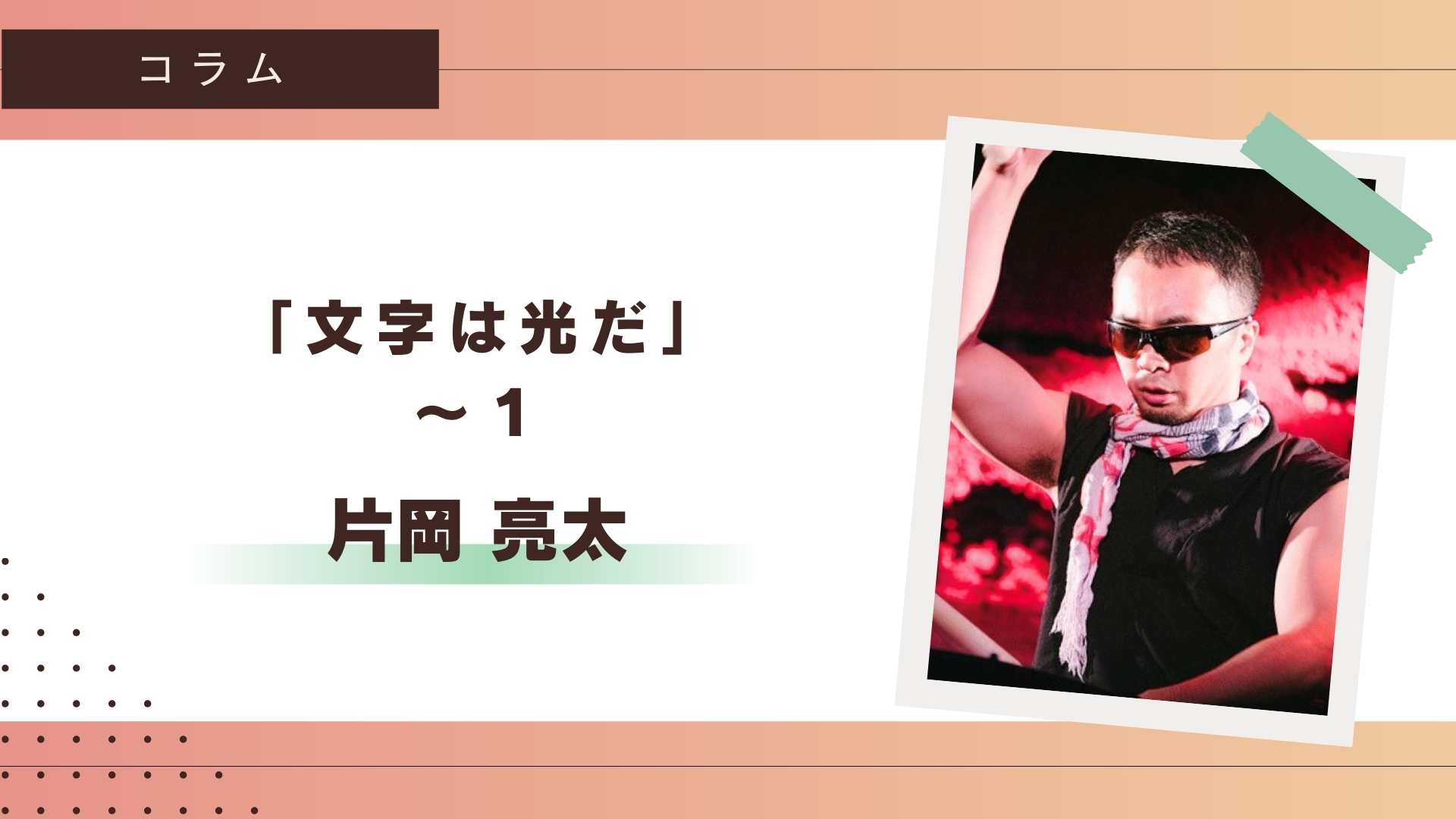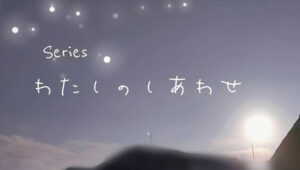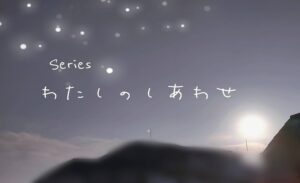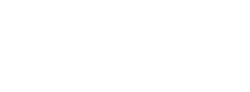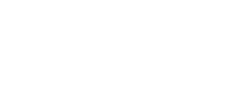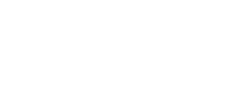「文字は光だ」~1
片岡亮太
本年1月10日に我が家から歩いて20分ほどのところにある「三島大社」へ初詣に行った時のこと。
春を思わせるほど温かな午後の日差しと、まだ少しお正月の残滓(ざんし)が漂っているように感じる空気の中、参拝を済ませ、帰ろうとすると、すぐそこには御神籤(おみくじ)が。
吉だ凶だとにぎやかな声を聞いているうちに久々に引いてみたくなりやってみたところ、なんと大吉!
みくじ箋(みくじせん、あの紙ってそう呼ぶのですね、今回調べて初めて知りました)を開き、中に書かれていることを妻に読んでもらうと、どうやら現在の僕は、あらゆることにおいて良い状態にある様子。
その言葉だけで心も体も元気になれそうだったので、これは枝に結ぶのではなく、お守りのつもりで手元に置いておくべきと考え、大事に折りたたんでお財布に入れてから帰路につきました。
その時、しみじみと思ったのです。
文字が書かれたものを積極的に持ち帰ろうと思えるだなんて、時代が変わったんだなあ…と。
数年前までは、どんなにありがたいことが書かれていようとも、内容を読んでくれる人が常に傍にいない限り、全盲の僕にとっては、みくじ箋もコンビニのレシートも対して変わりのない、ただの紙切れにすぎませんでした。
だから、意図せず捨ててしまって嫌な気持ちにならないためにも、領収書から手紙に至るまで、文字が書かれた紙は全て、できる限り家族に管理を任せ、手元にはおかないようにしてきました。
でも今は違う。
そこに何が書かれているかを知りたい時には、スマホのカメラをかざせばいい。
それだけで、アプリが文字情報を自動で認識し、音声で読み上げてくれます。
4年ほど前、この機能を持ったアプリを初めて入手した時、僕は「新たな目」を持ったと錯覚するほどに感動しました。
その年の年末、「いずれ家族に手伝ってもらって仕分けしよう」と思っているうちに、ものすごい量になってしまっていた、出演したイベントやコンサートのチラシ、
事務的な書類などを片っ端からスマホに読み上げさせ、大きなごみ袋に4袋分の紙たちを、「これはもう不要」と、確信したうえで処分した時の快感は、今でも忘れられません。
それから今日に至るまで、スマホを介しての、僕と紙に書かれた文字との付き合いは順調そのもの!
シンポジウムや講演を聞きに行った際、配布された資料の概要をざっと知りたければ、カメラを向けた瞬間に、アプリが読み上げる内容を一部聞くだけで、「ななめ読み」的に中身を把握することができるし、各所でいただく、
たくさんの名刺の内容を確認し、データとして保存しておきたければ、アプリの指示に従って、名刺を写真撮影し、検知された文字情報をコピーして、データで保存しておけば、メールアドレスや電話番号など、必要な情報を一覧で管理することができる。
近年は、同種のアプリの数も増加し、それぞれに機能のアップデートも行われているため、各アプリが持つ得意分野に合わせて、使用するものを選ぶことも可能。
例えば言語によって使い分けたり、書かれている内容だけでなく、そのデザインにも興味がある場合には、「見た目」の説明に秀でたものに切り替えるというようなことも良くあります。
最近では、一部手書きの文字を認識させられるようになったアプリまで出てきました。
思えば、弱視だった幼少期でさえ、こんなにも文字に親しんだことなんてありません。
唯一見えていた左目に0.04程度の視力しかなく、「矯正視力が0.3未満」とされる弱視の条件からすれば、弱視の中でも、見えていない方に属していたと思われる当時、学校で配られるプリントは、
拡大鏡などを使ってようやく何とか読めてはいたものの、新聞や雑誌に至っては、写真やイラスト、大きな見出し以外は、「無数の小さな点」くらいにしか見えていなかった僕。
(ちなみに余談になりますが、全盲とは、視力が0.01未満の状態を指し、目の前にある手の指の本数が見える「指数弁(しすうべん)」、目の前にある手が動いているか止まっているかがわかる「手動弁(しゅどうべん)」、
光がついているか消えているかがわかる「光覚(こうかく)」、光も認識できない視力0の状態の4段階があり、現在の僕はその中で、なんとか光覚は残っているかな?という程度の視力です)
だから、スマホさえあれば、どんなに小さな文字で書かれている書類であっても読むことができる今の状況は、人生で最も、紙媒体を楽しめているとも言えます。
活字を機械が認識する、それ自体が可能になったのは、ずいぶん前のこと。
記憶にある限りでも、20年以上前から、スキャナーや専用のデバイスを用いて、本や書類に書かれた文字情報を読み取り、データ化することはできました。
ただ、その頃は、精度が低かったり、作業のすべてを全盲の人が一人で行うには限界がありました。
その時代と比較したら、昨今のように、スマホ一台という手軽さで、一瞬にして、しかも独力で紙に書かれた文字にアクセスできるようになったことは、革命的と言っても過言ではないほどの変化です。
僕が大学生だった時には、専門書のように、ニーズが少ない本の場合には、ボランティア団体の方たちが作成してくださった点字や音読のデータが存在していないことがほとんど。
だから、4年生の時、卒論を作成する際には、同じ学科の後輩を中心とする学生たちに協力してもらい、一ページずつスキャナーで読み取り、間違いを修正したデータをメール等で送ってもらうという形で参考文献を読み、執筆を進めました。
そこまでの労力をかける時間的な余裕のない普段の授業の場合は、データ化が可能な資料については教授にメールで送ってもらったり、
それができないプリントや教科書はボランティア団体の方に点字にしていただくなど、なんとか文字情報にアクセスすべく、四苦八苦していたもの。
それでも、点字化が間に合わなかったり、教授がメールを送るのを忘れるなど、様々な理由により、聞いたこともない言葉が多発する授業を、資料がない状態で受けなければならないことはよくありました。
特に1年生の頃には、まだ様々な環境や大学側の対応などが整えられていなかったので、試験勉強に必要なプリントが、一切点字にできておらず、結果、単位を落としてしまったり、単位は取れたけれど成績が低かったことも。
そういう時には、「この結果は僕のせいではないのでは?」と不本意に感じていました。
毎日、欠席も遅刻もせず講義に出ている僕が、資料や教科書が手元にあるという、多くの学生にとって当たり前の環境で学ぶ、たったそれだけを実現するために、こんなにも苦労しているにもかかわらず、
他の人たちは皆、たとえ寝坊やアルバイト、サークル活動などが理由で遅刻してきたとて、教室に入って、印刷された資料を手にし、板書された内容を読めば、瞬時にその日の講義の内容を理解できてしまう。
その境遇の違いが悔しく、というか正直に言えば妬ましくさえ思えたこともあります。
そんな過去がある僕にとって、「2025年の当たり前」とは、まるでSF小説の世界の出来事。
未だに驚きの連続です。
当然、レイアウトが複雑で、アプリの認識がうまく機能しないことや、本を丸ごと一冊読むなどのように、自力では難しいこともまだまだたくさんあります。
それでも、かつては凹凸ひとつなく、何の意味も持たない、ただの紙切れにしか過ぎなかったものから、情報を得て、学んだり、笑ったりできる可能性は、今も広がり続けている。
まるで一枚の紙から発せられる光を吸収しているかのよう。
大げさかもしれませんが、僕は毎回そのくらい感激してしまうのです。
それは、約30年前、「点字との出会い」が僕に与えてくれた心の震えにも近いものであるように思います。
つづく
◆プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。