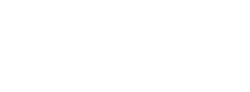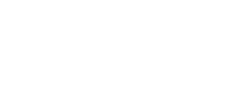「障害×運動×大きな夢」~1
片岡亮太
1
今から25年前、中学2年生だった時のこと。
僕は、目の手術のために、中3になる前の春休みの期間を利用して、静岡県立こども病院に約2週間の入院をしました。
まだ子供と言ってよい年齢での手術や入院と言うと、一般的には「気の毒」とか「可哀そう」という印象を持たれそうですが、実はこの時の入院は、そういったネガティブな感情とは無縁の「楽しい入院」でした。
原因の一つは治療の目的。
僕はそれ以前にも数回の手術を経験していたのですが、それらは全て、視力が改善することを願ってとか、目の異変による激痛の中、緊急で決まったりと、深刻なものばかり。
一方、この時の治療は、目の状態を安定させるべく行うことになっていたため、僕にとっては非常に気楽で、精神的にも余裕がありました。
確か、術後の痛みもさほどなかったように記憶しています。
その影響でしょう、手術直後、全身麻酔から目覚めたばかりで、起き上がることもできない状態だったにも関わらず、成長期真っ盛りでおなかが空いており、看護師さんに食べさせてもらう食事を、次から次に咀嚼しては飲み込んで、「大丈夫、気持ち悪くない?無理しなくていいんだよ、えっ?本当に大丈夫なの?」と何度も念を押されながらも、あっという間に完食するほどに元気でした。
「入院仲間」にも恵まれていました。
初めて手術を受けた9歳の時、同じ病室にいたことで仲良くなり、後の入院の際にも度々顔を合わせることになる、長期治療のために帰宅が叶わずにいた「顔なじみ」の少し年下の女の子をはじめ、同世代の男女が複数入院しており、毎晩のように消灯後に一部屋に集まっては、くだらない話ばかりしていて、時にはそこに看護師さんまで参加していたことは、良い思い出です。
特に、小さな盲学校(現 視覚特別支援学校)で日々を過ごしていた僕にとって、一般の中学校に通う年の近い人と当たり前に仲良くなれたことは、新鮮な経験でした。
あの頃に今のスマホのようなものがあれば、LINEの交換などをして、ずっと友達でいられたのにと、未だに残念に思うこともあります。
2
そんな入院終盤のこと。
退院するにあたり、術後の症状が落ち着くまでの間、生活の中で気を付けることについて説明を受けた際、とても印象深いことがありました。
話してくれたのは、今思えば研修医だったと思われる若い女性の先生。
その先生は、何の迷いもなくこう言いました。
「やらないと思うんだけど、しばらくは激しい運動はしないでね」
とてもにこやかな声でした。
その頃の僕はすでに和太鼓の演奏をしており、連日行う学校での仲間たちとの練習はもちろん、自宅でも、太鼓の代わりに厚手の表紙の雑誌をガムテープで勉強机に固定して、撥(ばち)でたたくなど、稽古をしていました。
さらに、母校の盲学校は当時、基礎体力作りとして、ひたすら走ることに注力していたため、朝から3~4kmほど走ることが当たり前。
それは、「安静」とは程遠い日常でした。
弱視だった10歳までの間に通っていた一般の小学校では、視力の低さや、あまり積極的ではなかった性格、さらには専門的な支援を十分に受けられる環境がなかったことなどが重なり、運動はからっきしだった僕。
そんな自分が、太鼓を除けば、さほど運動が好きだったわけではないにもかかわらず、毎日しっかり身体を動かして、それなりに筋肉質な体格になれていたことを、自信に感じていたからか、研修医の先生からの言葉を受け流すことができず、「いえ、激しい運動やってますよ」と、気付いたら普段の体力作りについてあれこれ語っていました。
その先生は、とても驚いた様子でしたが、「そうだったんだ。それじゃあそういう運動は1か月くらいは我慢してね」と改めて説明をしてくれたのですが、「眼科の先生さえも、全盲だと運動をしないと思うのか」と、憤りとも、傷ついたとも違う、何とも言えない気持ちになったことを今でもよく覚えています。
3
ただあの時同時に、心の片隅で、「そりゃあそうだよなあ」と思っている自分もいました。
なぜなら、僕自身、失明直後に、後に転入することになる盲学校を見学した際、自分と同じく全盲の児童・生徒たちが、当たり前のように運動をしている様子に、大きな衝撃を受けていたからです。
グラウンドの外周を、短いひもの両端を持った先生と生徒のペアが走り抜けていく足音、前を走る先生の肩に結ばれた鈴の音を頼りに、1~2メートル後ろを走りながら楽しそうに会話している別のペアの声、学校の案内をしてくれていた先生から聞いた「視覚障害の人が行うスポーツがいっぱいあるんだよ。体育の時間でやるから楽しみにしていてね。」という言葉、休み時間になった途端に、廊下や階段をすごい勢いでばたばた駆け抜ける同世代の視覚障害のある子供たちの様子…。
耳に飛び込むすべてがとても眩しく思えました。
あんなことが自分にもできるのだとしたら、目が見えない状態での生活とは、僕が想像しているものとはだいぶ違うものになるのかもしれない。そう思い、希望を抱いた瞬間のことを僕は一生忘れません。
4
失明当初の僕や、あの日の研修医の先生の中に存在していた、「目が見えない人は運動ができない」という前提、それは、現在も根強く残るある種の「偏見」ではないでしょうか。
実際、各地に演奏へ伺うと、舞台を見てくださった方が、技術云々ではないところで驚かれることが多々あります。
その驚きとは、「目が見えないのにあんなに速く、大きく身体を動かしているなんて!」というもの。
僕が演奏している姿と、イメージの中の視覚障害者との間に生まれる齟齬が、違和感と共に、驚きという感情を呼び起こしているようです。
僕には手足の障害はないのだから、全身を高速で動かしながらダイナミックに和太鼓を打っていたとて、本来は何の不思議もありません。
にもかかわらず、無意識のうちに、全盲の人には激しい動きは難しいと思ってしまうのは、ひとえに「そういう姿を見る機会がない」からなのでしょう。
おそらく多くの人にとって、全盲の人を見かけるシチュエーションは町中や駅。
その全盲の人は、白杖(はくじょう)や盲導犬を使用したり、あるいは誰かの腕や肩に触れながら歩いている。
歩調は、世間の平均速度よりは遅いはず。
それは杖先の振動や、盲導犬、誘導してくれている人の動きを通じて、段差や歩く方向、障害物の有無などの周囲の情報を取得する必要のある僕たちにとって、目が見えている人ほどの速さで歩くことには危険が伴うからです。
例え慣れた道であっても、何かにぶつかった際、怪我をしない程度の速度をキープし、慣れない場所なら緊張した雰囲気と慎重な足取りで歩く。
そういう様を見ていると、視覚障害者を、「速さ」や「堂々とした動き」と関連しづらくなるのは無理もないことなのかもしれません。
ご自身の目が見えなくなることを想像し、「その状態で運動なんて絶対に無理だ!」と考えてしまうことの影響もあるように思います。
ただ、そのような意識とは、気を付けていないと、障害があることと「か弱さ」とか「消極性」、「もろさ」などとを結びつけ、「障害者」イコール「弱者」という図式を助長する端緒にもなりかねません。
和太鼓は、音楽であると同時にスポーツの要素も感じるほど、身体の動きも見てもらえる楽器です。
そんな和太鼓による、力強い音と全身を駆使したアクションが生み出す演奏を通して、視覚障害と運動についての「思い込み」を揺さぶることができたら、それは、僕だからこそできる、社会に一石を投じる手段になり得るのではないかと、最近よく考えます。
「えっ?本当に見えてないの?」
ステージ序盤にはそのように感じていた人の心を、音楽にぐっと引き込み、いつの間にか障害のことなど忘れ、演奏に没頭してもらった結果、最終的には「そう言えばあの人、眼が見えないって言ってたなあ」と思う。
そんなパフォーマンスは、どんな言葉よりも雄弁に、何かを伝えられるのではないか。
それはきっと、「障害者」と「弱者」とを繋ぐものを断ち切る一助になる。
だから僕は、今日も熱い思いと共に、力強く撥を振るのです。
◆プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。