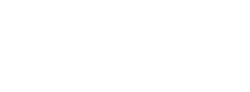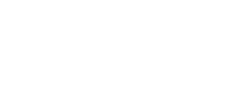『40歳の地図』
わたしの
二十歳くらいのときは地図なんていらなかった。
と言っても、これはメタファーではなくて、本当に地図がなくても太陽の方向や傾き加減で自分の位置を把握することができていたし、目的地がどっちの方角にあるのか分かった。
自分の中に羅針盤があった。
当時はスマートフォンはなかったし、もちろんグーグルマップもない。
辛うじて携帯電話が流行り始めた頃で、(懐かしい人もいるかもしれない)ドコモのiモード全盛期だった(私は持っていなかったけど)。
22歳になって400CCのバイクを買ったとき、一冊の地図を買った。関東の道路地図。
目的地への行き方を確認するためにもちろん使ったが、道路の名前を覚えたり、位置関係を把握するために雑誌を読むように部屋で眺めて過ごしていた。
地図を読むのが好きだった。
経路をしっかり記憶してその通りに行くことは重要視していなくて、やっぱりほとんどは地図を見ずに自分の方向感覚を頼りにして走り、後になって地図を読み返して自分の辿ってきた道路をおさらいするのが楽しかった。
道路の名前、交差点の名前を確認しながら、実際に走って実感した(この目で見た)雰囲気を思い返し、味わうのがおもしろい遊びだった。
その地図は相棒で、リュックにいつも入れて一緒に行動していた。
学生時代が終わり、就職せずにフラフラとしていたとき、自分は風来坊の素質がなくて何もすることがないということに居ても立ってもいられずに、かといって仕事をするだけの心構えもできていなくて悶々とするようになって、離れて暮らしてはいたが親から自立できず、甘ったれている自分に嫌気もさし、みんなに迷惑をかけていると思い込んで自尊心は醜く縮こまって卑屈になっていた。
そしてバイクに乗って風切る気分でもなくなってしまい、バイクを売った。二束三文にしかならなくて悲しかった。
バイクを売った日、板橋区のバイク屋から帰りはもうバイクがないので電車に乗るしかないのだが、なんだかそれも嫌で、バイクを売って得たわずか3万円を握りしめて、当時住んでいた上池袋までとぼとぼと歩いて帰った。
すっきり晴れた冬の一日。その午前中の空の青さに胸が痛かった。
何してるんだろうな、と思った。空しかった。その頃、ずっと空しさが付き纏っていた。
◇
20代後半で仕事のまねごとをするようになって、移動するために250CCのオンボロ中型スクーターを買った。
フュージョンやマジェスティのようなビッグスクーターブームだったが、流行りに乗れないへそ曲がりの性格ゆえ、フュージョンの原型となった古いスクーターを選んだ。リュックに入れて持ち歩いていた地図の居場所は今度はスクーターの座席の下の荷物入れに移った。
ハンドルの下に方位磁石を付けて、その方角を頼りにどこまでも出かけた。5年くらいは乗っていただろう。
ある日、仕事中に倒れて救急で運ばれた友人が病院で息をひきとって、深夜だったので電車もバスも走っていなかったのでこのときもまた自宅に帰るためにとぼとぼ歩いていたのだが、途中でバイク事故が起こり、それを見た次の日からスクーターに乗るのをぴたりとやめた。
急に怖くなったという思いはなかったのだが、そう意識されなかっただけで本当は怖かったのかもしれない。
エンジンをしばらくかけずにいたら、いつのまにかオンボロバイクは動かなくなってしまい、引っ越しのとき専門の回収業者に引き取ってもらった。
◇
30代中頃になってはじめて車を購入したとき、標準装備としてカーナビがついていた。
相棒の地図はもうすっかりボロボロになってしまっていて、破れている個所はテープで補強してある。
さすがにリュックに入れて常に持ち歩いてはいないけれど、車の助手席の裏面のポケットに突っ込んである。
そこから取り出すことはなくて、ほとんどお守りがわりに一緒に車に乗っているようなものである。カーナビを見ることに慣れてしまった。
時々職場でカーナビがついていない車に乗ることがあると、ついていないにもかかわらず、チラチラとカーナビを確認する動きをしてしまう。
目的地を目指して走りながら、不安になってカーナビに目をやろうとしてしまうのだ。カーナビがないと道が分からない。
もう、自分の中の羅針盤が失われてしまって、太陽や影の位置でも、なんとなくな感覚でも、方向が分からなくなってしまった。
地図を読むのも苦労するようになってしまった。
カーナビは、人類の叡智、最新科学を組み合わせて作られたもののはずで、滅茶苦茶便利なものには違いないのだろうけれど、おかげで失われたものもある。
自分の中に備わっていたコンパスを取り出して、外付けにしてしまったようなものである。
それをもう一度取り込もうとしてもできない気がする。
できたとしても、長い時間と非常に大きなエネルギーが必要だろう。
何かの民俗学の本で読んだことがあるのだが、アメリカ大陸の原住民は、呼吸するだけで微妙な大気の湿り気を感じ分け、雨が降るかどうかを知ったという。
都会に暮らす近代人は驚いたそうだが、原住民にとってみればこれだけ自然が教えてくれているのに、どうして分からないのか逆に不思議だったそうだ。
天気予報という情報はいらなかったのである。だからテレビ番組もスマートフォンも、アプリも必要なかった。
技術は進歩したのかもしれないが、それらを手に入れる度に自然とともに生きる人間としては確実に退化している。退化とも違うのだろうか、自然から離れ、孤立していくように感じてしまうのは自分だけだろうか。