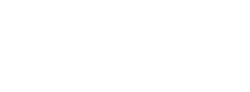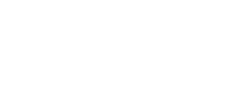「境界線を越えて」後編
片岡亮太
渡米前の僕にとって横断歩道をわたる瞬間、車とはいつでも恐れと警戒の対象でしかありませんでした。
日本で、車に乗っている人から信号が変わったことを教えてもらった記憶はあまりないし、停車している車にぶつかりそうになったり、実際にぶつかってしまった場合など、聞こえるのは軽く押されたクラクションの音であることがほとんど。
アメリカと比べると日本は、「歩行者」と「車」という境界線が濃いのかもしれません。
もしも僕が、あと数年ニューヨークに住んでいたなら、きっと周囲に歩行者がいない状態で横断歩道を渡る時には、近くの車に向かって、「青ですか?」と声をかけて聞くことができるようになっていただろうとよく想像します。
そのように考えるのは、身近にまさにそんな風に生活している人がいたからです。
それは、ニューヨークでパーカッションのレッスンをしてくれていたヴァンダレイというブラジル人のジャズドラマーで全盲の男性。
彼は自宅で僕を指導してくれた後、最寄りのバス停までよく見送ってくれました。
そんな時は、いつも大きな音で白杖を路面に打ち付け、「亮太こっちだ、ついてこいっ!!」と楽しそうに声を張り上げ、バス停手前の大通りに差し掛かれば、「誰か、この道渡らないか!?」と、数10メートル先にまで聞こえそうな声を出し、それを聞いて近づいてきた人に、実に紳士的に、「彼を向こうのバス停まで連れて行ってください。ありがとう、よろしくお願いします。亮太、じゃあな!」と言って去って行く。
それが当たり前の光景でした。
僕は彼のあの豪快さや明るさ、白杖を使って歩くことも、誰かに誘導を頼むことも、決して迷惑や恥じることではなく、自然なこととして受け入れている、まさに「ボーダーレス」な姿と、そんな彼との間に何の隔たりも感じさせることなく関わるニューヨーカーたちの様子が大好きだったし、あこがれてもいました。
今でもその気持ちに変わりはありません。
ただ、日本でニューヨークのヴァンダレイのようにふるまうことには大きな抵抗があります。
それは、街中に僕のような視覚障害者がいることや、障害から派生する不自由を助けてもらうことを、まだまだ「当たり前」のこととして社会全体が認識しているとは思いづらいからです。
そんな意識を垣間見ることのできる例として、音響式信号の音が鳴る時間帯の問題があります。
各地に設置されている音響式信号の多くは、夜遅く、あるいは早朝には音が鳴ってくれません。
それは、ボタンで作動するタイプの音響式信号も同様。
理由は、周囲で暮らす人にとってうるさいから。
これまで何人かの友人が生活県内の信号機について、「音量を下げてもいいから、時間帯に制限なく、ボタンを押したら音が出るようにしてほしい」と自治体に要望を出しても、上記の理由から断られたという体験談を聞いて驚きを隠せませんでした。
粘り強く交渉した結果、作動する時間帯が長くなったり、ボリュームを下げて音が鳴るようにしてもらえたというケースもあるようですが、そのことを素直に喜べない自分がいました。
横断歩道を安全に渡れるかどうかは命にかかわる問題。
それと「周囲への迷惑」とは、同じ天秤にかけられる問題であるとは、僕には思えません。
共生社会の実現について考えた時、一つのキーワードになる言葉に「ノーマライゼーション」があります。
これは、多くの人にとって当たり前であることをマイノリティの人にも保証していこうという考え方です。
その視点に立った時、日本で暮らすほとんどの人が、日々当たり前に安全を確認しながら渡っている横断歩道を、視覚障害者はまるで地雷原に足を踏み入れるかのごとく、常に死や負傷の可能性を感じながら進まねばならない現状は、ノーマライゼーションからは程遠いと言わざるを得ません。
近年、技術の進歩によって、スマホのアプリが一部の信号の色を認識できるようになり始めており、その確実性と利用範囲が広がっていけば、間違いなく僕たちの安全は確保しやすくなるでしょう。
けれど、僕が住んでいた頃、ハーレムの横断歩道にはそんなシステムはおろか、音響式の信号さえ一台も設置されてはいませんでした。
ニューヨークの人たちが、たった一言の声かけによって解消していたことを、どうして僕たちは容易に超えられないのだろうか?
そのことにもどかしさを抱いています。
こんな風に言葉を綴っている僕自身、遠く離れたニューヨークを自由に歩くことはできていたのに、中学時代にトラックに轢かれかけた近所の横断歩道を自力で渡ることがどうしても怖くて、いまだに地元を1人で歩くことができません。
そのことに対し、音響式信号の設置を求めることを含め、改善のための動きを起こすことが一切できておらず、壁を壁のままにしてしまっていることを、折に触れて情けなく感じています。
コロナ禍によって、それまでのように遠方に出かけることができなくなった時、気晴らしのための散歩さえ一人きりではできないことに気づき、自宅周辺を独力で歩けるよう訓練したり、環境を整えることを後回しにし続けてきたことを後悔しました。
演奏や講演のために日々各地へ出向いているため、地元にとどまっている時間がほとんどないことや、結婚し共に歩いてくれるパートナーを得たことを言い訳にして目を背けていた現実を突きつけられているようでした。
だからこそ、社会同様、僕もまた変わっていきたいと痛切に感じています。
歩行者と車という立場の違い、障害の有無、遠慮や恥ずかしいという気持ち、人命と迷惑の天秤…。
「共生」という目的地に向かって歩く僕達の前に広がる横断歩道には、まだまだ何本もの「境界線」という名の車道が横たわっていますが、あの日、ニューヨークの交差点で車を降りて僕のもとに歩み寄ってくれた女性のように、既存の社会通念や価値観、今それぞれが感じている当たり前の図式にとらわれることなく、たくさんの「境界線」を越えて考え、行動できた時、進路を妨げていた車は止まり、信号の青いライトが力強く輝くのかもしれません。
プロフィール
片岡亮太(和太鼓奏者/パーカッショニスト/社会福祉士)
静岡県三島市出身。 11歳の時に盲学校の授業で和太鼓と出会う。
2007年 上智大学文学部社会福祉学科首席卒業、社会福祉士の資格取得。
同年よりプロ奏者としての活動を開始。
2011年 ダスキン愛の輪基金「障害者リーダー育成海外研修派遣事業」第30期研修生として1年間単身ニューヨークで暮らし、ライブパフォーマンスや、コロンビア大学内の教育学専攻大学院ティーチャーズ・カレッジにて、障害学を学ぶなど研鑽を積む。
現在、国内外での演奏、講演、指導等、活動を展開。
第14回チャレンジ賞(社会福祉法人視覚障害者支援総合センター主催)、
第13回塙保己一(はなわ ほきいち)賞奨励賞(埼玉県主催)等受賞。